「 自分の考えを改めるべき場面 」 一覧
-
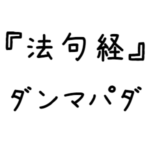
-
『法句経』ダンマパダ - ブッダ 真理の言葉
2023/06/15 -仏教を本気で学ぶ
03月13日, し, た, ひ, ふ, ダンマパダ, 心を整えるのは難しいこと, 生あるものに利益を与えることを行う, 自分の考えを改めるべき場面かの尊師・真人・正しく覚った人に敬礼したてまつる。 【 第1章 ひと組みずつ 】 1 物事は心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその ...
-
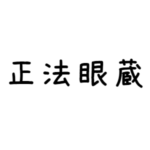
-
「正法眼蔵」道心(どうしん)
2020/09/24 -仏教を本気で学ぶ
と, 何を基準に物事を見ているか, 念仏, 正法眼蔵, 自分の考えを改めるべき場面, 菩提心この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
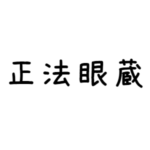
-
「正法眼蔵」生死(しょうじ)
2020/09/24 -仏教を本気で学ぶ
し, 仏祖になった人の生き方, 何を基準に物事を見ているか, 夾山善会, 定山神英, 正法眼蔵, 自分の考えを改めるべき場面, 身と心が両方いっしょに道を得るこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
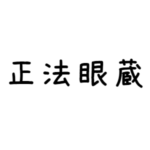
-
「正法眼蔵」三時業(さんじごう)
2020/09/24 -仏教を本気で学ぶ
お釈迦様(ブッダ), さ, アジャータシャトル, サーリプッタ, デーヴァダッタ, モッガラーナ, 仏祖になった人の生き方, 南泉普願, 慧可, 正法眼蔵, 生あるものに利益を与えることを行う, 自分の考えを改めるべき場面, 長沙景岑, 闍夜多, 阿逸多, 鳩摩羅多この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
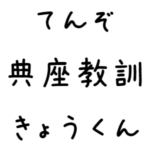
-
『典座教訓』18、自然のまま喜びの心で引き受ける
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
08月07日, し, その時その時を大事にする, 世間の物差しで考えない, 典座教訓, 目の前の人のために出来ることをする, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
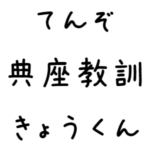
-
『典座教訓』15、全て行ずることが仏事
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
08月04日, す, その時その時を大事にする, 典座教訓, 建仁寺-京都府京都市東山区, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
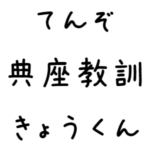
-
『典座教訓』11、よく自分のことを勤める
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月31日, その時その時を大事にする, よ, 中国の寺院の様子, 典座教訓, 自分の考えを改めるべき場面, 道元禅師この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
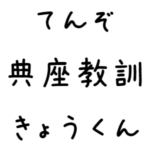
-
『典座教訓』10、他人のしたことは自分のしたことにならない
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月30日, た, 世間の物差しで考えない, 中国の寺院の様子, 典座教訓, 物事を始めるタイミング, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
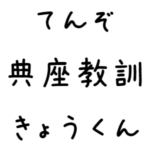
-
『典座教訓』6、よし悪しの隔てなく授かる心
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月26日, よ, 典座教訓, 分け隔てする心を改める, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
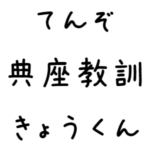
-
『典座教訓』5、菜っ葉も伽藍も上下なし
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月25日, な, 何を基準に物事を見ているか, 典座教訓, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』70、学人第一の用心は先ず我見を離るべし
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月14日, か, ひたすら坐禅することの重要性, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』85、学道の人は吾我のために仏法を学する事なかれ
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月28日, か, 中国の寺院の様子, 仏祖になった人の生き方, 何を基準に物事を見ているか, 余計なものを貯えずに生きる, 徳が外にあらわれるということ, 正法眼蔵随聞記, 自分のことばかり考えずに名誉心をも捨てる, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』101、大慧禅師の云く
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
07月14日, そのままを理解する, た, 分け隔てする心を改める, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』104、古人の云く百尺の竿頭にさらに一歩を進むべし
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
07月17日, こ, 世間の物差しで考えない, 正法眼蔵随聞記, 自分のことばかり考えずに名誉心をも捨てる, 自分の考えを改めるべき場面, 評価されることを望まない, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』106、学人各々知るべし
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
07月19日, か, どんな言葉で話せばいいか, 人は影響し合う, 建仁寺-京都府京都市東山区, 徳が外にあらわれるということ, 正法眼蔵随聞記, 物質的に豊かではない事のメリット, 目の前の人のために出来ることをする, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』27、祖席に禅話を覚り得る故実
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月02日, そ, そのままを理解する, 何を基準に物事を見ているか, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』38、唐の太宗の時
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月13日, と, 余計なものを貯えずに生きる, 徳が外にあらわれるということ, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』39、学道の人は人情をすつべきなり
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月14日, か, そのままを理解する, 仏祖になった人の生き方, 何を基準に物事を見ているか, 正法眼蔵随聞記, 自分のことばかり考えずに名誉心をも捨てる, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』97、世間の人自ら云く
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
07月10日, せ, どんな聞き方をすればいいか, 仏祖になった人の生き方, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』55、治世の法は上天子より
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月30日, し, そのままを理解する, その時その時を大事にする, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』14、俗の帝道の故実を言うに
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』17、人その家に生まれ、その道に入らば
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
04月22日, ひ, ひたすら坐禅することの重要性, 正法眼蔵随聞記, 物事を始めるタイミング, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』74、学道の人、悟りを得ざる事は
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月17日, か, そのままを理解する, 世間の物差しで考えない, 悟り, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』73、俗人の云く何人か厚衣を欲せざらん
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月16日, そ, 正法眼蔵随聞記, 物質的に豊かではない事のメリット, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』75、学人初心の時
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月18日, か, 仏祖になった人の生き方, 分かったと思ったことはそのままにせず様々な点から考え直す, 正法眼蔵随聞記, 物事を始めるタイミング, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』76、愚癡なる人は
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月19日, く, どんな言葉で話せばいいか, 正法眼蔵随聞記, 自分のことばかり考えずに名誉心をも捨てる, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』58、学道の人身心を放下して
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月02日, か, 仏祖になった人の生き方, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 身と心が両方いっしょに道を得るこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』69、学道の人自解を執する事なかれ
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月13日, か, そのままを理解する, 分かったと思ったことはそのままにせず様々な点から考え直す, 南陽慧忠, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』32、世人多く善事を成す時は
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月07日, よ, 他人の評価を気にするのはやめよう, 分け隔てする心を改める, 外見でその人を判断してはいけない, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』35、学道の人、世情を捨つべきについて
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月10日, か, 正法眼蔵随聞記, 物事を始めるタイミング, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』44、学道の人、世間の人に智者もの知りと知られては無用なり
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月19日, か, ただ一つの事に向き合う, 何を基準に物事を見ているか, 教える人の心構え, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』45、今この国の人は
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月20日, い, 世間の物差しで考えない, 他人の評価を気にするのはやめよう, 何を基準に物事を見ているか, 分け隔てする心を改める, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。