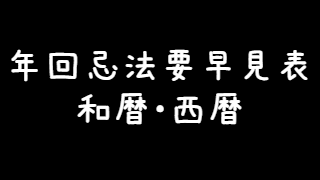中島法雄
中島法雄 自動化を目指す時代に生きて②
前回、私たちが生きているのは無意識に自動的に働いてくれる身体があるからという話をしました。ところで、私は一般家庭からお寺の世界に入ったのですが、お寺の仕事と言えば何を思い浮かべますか?お葬式や法要でお経を唱えて、坐禅をして、鐘を叩いて、一般的なイメージはそんなところでしょうか。師匠とは50歳離れていて、その奥さんが亡くなってから住み込みで働いたので、その他に炊事洗濯掃除などの家事、畑仕事、電話対応、パソコン管理、事務全般、思いつくだけでこれだけですね。実質24時間勤務です。禅寺だったので、精進料理というイメージを持つ人もいると思いますが、自給自足の精神も受け継がれていて、畑仕事をするお寺もあり...

-wikipediaより.jpg)