「 その時その時を大事にする 」 一覧
-
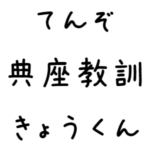
-
『典座教訓』18、自然のまま喜びの心で引き受ける
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
08月07日, し, その時その時を大事にする, 世間の物差しで考えない, 典座教訓, 目の前の人のために出来ることをする, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
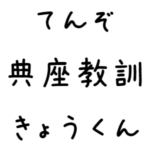
-
『典座教訓』17、ただ自然に変わっていくだけ
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
08月06日, その時その時を大事にする, た, 何を基準に物事を見ているか, 典座教訓この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
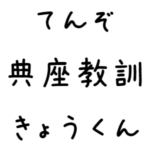
-
『典座教訓』16、自他の境をとりはずす
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
08月05日, し, その時その時を大事にする, 中国の寺院の様子, 仏祖になった人の生き方, 典座教訓, 洞山良价, 目の前の人のために出来ることをするこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
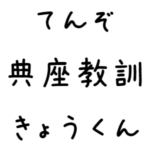
-
『典座教訓』15、全て行ずることが仏事
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
08月04日, す, その時その時を大事にする, 典座教訓, 建仁寺-京都府京都市東山区, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
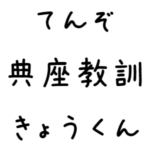
-
『典座教訓』11、よく自分のことを勤める
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月31日, その時その時を大事にする, よ, 中国の寺院の様子, 典座教訓, 自分の考えを改めるべき場面, 道元禅師この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
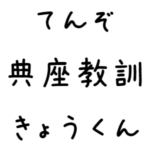
-
『典座教訓』9、食べることも仏法を行じていること
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月29日, その時その時を大事にする, た, 世間の物差しで考えない, 仏祖になった人の生き方, 余計なものを貯えずに生きる, 典座教訓この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
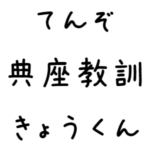
-
『典座教訓』4、心を他のことに移さない
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月24日, こ, そのままを理解する, その時その時を大事にする, ただ一つの事に向き合う, 典座教訓この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
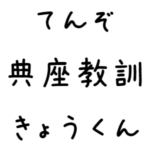
-
『典座教訓』2、心が整えば味も整う
1237/08/13 -仏教を本気で学ぶ
07月22日, こ, その時その時を大事にする, ただ一つの事に向き合う, 中国の寺院の様子, 典座教訓, 心を整えるのは難しいことこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』72、嘉禎二年臘月除夜
1236/12/31 -仏教を本気で学ぶ
1236年, 12月31日, か, その時その時を大事にする, ひたすら坐禅することの重要性, 人は影響し合う, 仏祖になった人の生き方, 孤雲懐奘, 正法眼蔵随聞記, 洞山良价, 興聖寺-京都府宇治市, 菩提達磨大師, 薬山惟儼, 阿難, 麻三斤この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』46、学人問うて云く某甲なお学道心に繋けて
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月21日, か, そのままを理解する, その時その時を大事にする, ただ一つの事に向き合う, 中国の寺院の様子, 何を基準に物事を見ているか, 正法眼蔵随聞記, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』92、古人多くは云く光陰虚しく度る事なかれ
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
07月05日, こ, その時その時を大事にする, ただ一つの事に向き合う, ひたすら坐禅することの重要性, 他人の評価を気にするのはやめよう, 正法眼蔵随聞記, 自分のことばかり考えずに名誉心をも捨てる, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』48、古人云く朝に道を聞かば夕に死すとも可なり
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月23日, こ, その時その時を大事にする, 正法眼蔵随聞記この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』66、学道の人は先ずすべからく貧なるべし
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月10日, か, その時その時を大事にする, 中国の寺院の様子, 正法眼蔵随聞記, 物質的に豊かではない事のメリットこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』79、世間の人多分云く
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月22日, せ, その時その時を大事にする, 何を基準に物事を見ているか, 正法眼蔵随聞記, 物事を始めるタイミングこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』96、先師全和尚入宋せんとせし時
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
07月09日, せ, その時その時を大事にする, 他人の評価を気にするのはやめよう, 何を基準に物事を見ているか, 正法眼蔵随聞記この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』34、今の世、出世間の人
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月09日, い, その時その時を大事にする, 他人の評価を気にするのはやめよう, 心を整えるのは難しいこと, 正法眼蔵随聞記, 生あるものに利益を与えることを行う, 自分のことばかり考えずに名誉心をも捨てるこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』55、治世の法は上天子より
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月30日, し, そのままを理解する, その時その時を大事にする, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』82、ある客僧の云く、近代の遁世の法
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
06月25日, あ, その時その時を大事にする, 仏祖になった人の生き方, 正法眼蔵随聞記, 物質的に豊かではない事のメリットこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』49、学人は必ずしも死ぬべき事を思うべし
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』52、人の鈍根と云うは、志の到らざる時の事なり
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
05月27日, その時その時を大事にする, ひ, 正法眼蔵随聞記, 自分の考えを改めるべき場面, 重要な話この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
『正法眼蔵随聞記』6、学道の人は後日を待って行道せんと思う事なかれ
1235/06/11 -仏教を本気で学ぶ
04月11日, か, その時その時を大事にする, 布薩, 正法眼蔵随聞記, 物事を始めるタイミング, 病気の時の学び方この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
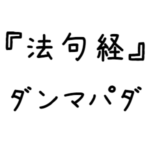
-
『法句経』ダンマパダ【 第2章 励み 】
0202/05/30 -仏教を本気で学ぶ
03月14日, その時その時を大事にする, は, ダンマパダこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
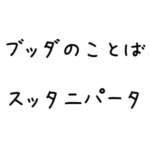
-
スッタニパータ【第1 蛇の章】6、破滅
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
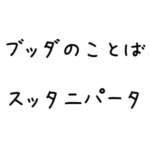
-
スッタニパータ【第2 小なる章】4、こよなき幸せ
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
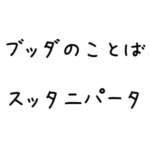
-
スッタニパータ【第2 小なる章】10、精励
0202/05/28 -仏教を本気で学ぶ
01月22日, し, その時その時を大事にする, ひたすら坐禅することの重要性, スッタニパータこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
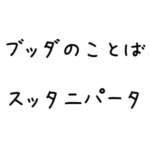
-
スッタニパータ【第2 小なる章】11、ラーフラ
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
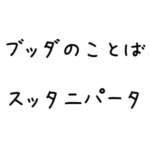
-
スッタニパータ【第4 八つの詩句の章】1、欲望
0202/05/28 -仏教を本気で学ぶ
02月08日, その時その時を大事にする, よ, スッタニパータこの投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。