「 さ 」 一覧
-
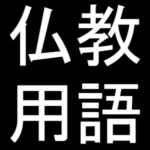
-
仏教用語/人物集 索引
2024/10/21 -仏教を本気で学ぶ
あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, さ, し, す, せ, そ, た, ち, つ, て, と, な, に, ぬ, ね, の, は, ひ, ふ, へ, ほ, ま, み, む, め, も, や, ゆ, よ, ら, り, る, れ, ろ, わ, んこのウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。
-

-
サンカーシャ - ブッダ三道宝階降下の地(僧伽舎)
サンカーシャはブッダ三道宝階降下の地として仏教の八大聖地の一つに数えられます。音訳して僧伽舎(そうぎゃしゃ)とも書かれます。サヘート・マヘートにある祇園精舎の香堂(ガンダクティー)からブ ...
-

-
サールナート - ブッダが教えを説き始めた地(鹿野苑)
サールナートはブッダが教えを説き始めた地として仏教の四大聖地および八大聖地の一つに数えられます。その教えを説いた相手は五比丘だと伝えられています。サールナートのうち鹿野苑(ろくやおん)だったとされる場 ...
-

-
身・口・意の三業(さんごう)
食べる、寝る、座る、立つ、歩く、走る。 身体で表すどんな動きも自分以外のものに影響を与えています。また、自分以外のものや環境から影響を受けて自分の身体が動いています。 言葉で表すどんなことも正しく伝わ ...
-

-
戒・定・慧の三学(さんがく)
三学(さんがく)とは、ブッダによって示された、修行者が必ず修めるべき3つの基本的な修行項目のことです。三勝学(さんしょうがく)ともいわれます。戒学、定学、慧学の3つを指して三学といいます。この戒、定、 ...
-

-
仏教三大聖木(無憂樹・菩提樹・沙羅双樹)
仏教三大聖木とは、ブッダ誕生の花である無憂樹(むゆうじゅ)、ブッダ悟りの木である菩提樹(ぼだいじゅ)、ブッダ入滅(にゅうめつ)の木である沙羅双樹(さらそうじゅ)のことをさします。 << ...
-
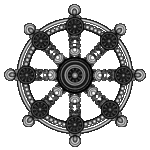
-
娑婆(しゃば)
娑婆とは、私たちの住むこの現実世界を指す言葉です。saha の音写。 << 戻る
-
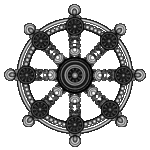
-
三結(さんけつ)
三結とは、四向四果の内の預流果を得る人の断ずべき三種の煩悩のことで、「見結」「戒取結」「疑結」のこと。「結」は煩悩の異名です。巴語(パーリ語)でtini samyojanani 、三つの束縛という意味 ...
-

-
三帰依文(さんきえもん)
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi (巴語(パーリ語)) ブッダン サラナン ガッチャ ...
-
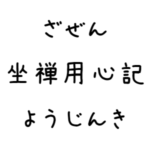
-
『坐禅用心記』(ざぜんようじんき)/瑩山禅師
正和元(1312)年、瑩山禅師は能登(石川県)に永光寺(ようこうじ)を開き、そこで『坐禅用心記』を撰述しました。坐禅の心得を説いた指導書で、『普勧坐禅儀』と共に参禅する者にとって欠くことのできない教説 ...
-

-
坂本龍一(さかもとりゅういち)
2023/03/28 -人物
01月17日, 03月28日, 2023年, さ, 坂本龍一, (命日)03月28日, (生誕)01月17日坂本龍一は作曲家・編曲家・ピアニスト・音楽プロデューサー。東京都出身。 イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のメンバーとして細野晴臣、高橋幸宏と共に国内外で活躍。矢野顕子、忌野清志 ...
-

-
佐藤蛾次郎(さとうがじろう)
2022/12/09 -人物
08月09日, 12月09日, 2022年, さ, 戒名, (命日)12月09日, (生誕)08月09日俳優・タレント。大阪府高石市出身。E・NESTO所属。息子は俳優の佐藤亮太。 1968年の映画「吹けば飛ぶよな男だが」で山田洋次監督に見いだされ、「男はつらいよ」シリーズで渥美清さん演じ ...
-

-
三遊亭円楽(6代目)(さんゆうていえんらく)
2022/09/30 -人物
02月08日, 09月30日, 2022年, さ, 三遊亭円楽(6代目), 戒名, 釈迦尊寺-群馬県前橋市, (命日)09月30日, (生誕)02月08日落語家、日本の俳優。東京都墨田区出身。出囃子は『元禄花見踊』。本名は會泰通。五代目圓楽一門会所属で、幹事長を務める。2017年6月27日から、客員として落語芸術協会に加入し、2つの噺家団 ...
-

-
懴悔文(さんげもん)
我昔所造諸悪業(がしゃくしょぞうしょあくごう) 皆由無始貪瞋痴(かいゆうむしとんじんち) 従身口意之所生(じゅうしんくいししょしょう) 一切我今皆懺悔(いっさいがこんかいさんげ) 【読み下し文】 我れ ...
-

-
仏の三十二相(さんじゅうにそう)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
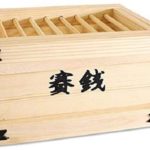
-
賽銭泥棒(さいせんどろぼう)
賽銭泥棒とは、お寺や神社にお参りに行った時に、お賽銭が入っている賽銭箱からお金を盗む行為です。また、仏像などの前に賽銭として置いているものや池の中に投げ込まれた賽銭などを盗むことも同様で ...
-

-
忉利天(とうりてん)- 三十三天
忉利天とは、仏教世界観における天の1つで、欲界の六欲天の内の第2天です。須弥山(しゅみせん)の頂上にあり、その東西南北にそれぞれ8つの城、中央に善見城(ぜんけんじょう)があり、合計33の ...
-
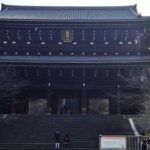
-
三門・山門(さんもん)
仏教寺院において正式な入口のことを三門または山門といいます。空門(くうもん)、無相門(むそうもん)、無作門(むさもん)の三境地を通って境内に入るという意味で三解脱門(さんげだつもん)とも ...
-

-
三黙道場(さんもくどうじょう)
三黙道場とは、坐禅を組み、食事を食べ、睡眠する僧堂(坐禅堂)、トイレをする東司(とうす)、お風呂に入る浴司(よくす)の三か所で、誰とも話をせずに静かに行動する場所のことです。気持ちが緩み ...
-

-
斎食(さいじき)
斎食とは、① 正午を過ぎてから食事しないよう午前中にとる食事、② 正午や決まった時間にとる食事、③ 法要など仏事の時に出す食事、④ 精進料理、⑤ 寺で出される食事のことをいいます。 ① ...
-
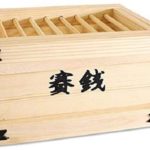
-
賽銭箱(さいせんばこ)
賽銭箱とは、お寺や神社にお参りに行った時に、お賽銭を入れるための箱であり、お賽銭を受けるための箱です。主に木製で、ステンレス製のものもあります。 賽銭箱に書いている文字 ・お賽銭 ・賽銭 ...
-
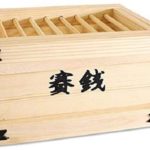
-
お賽銭(おさいせん)
お賽銭とは、お寺や神社にお参りに行った時に、賽銭箱などへお金を入れることです。ただし、2つの意味があります。一般参拝客にとっては、自分のお願いを聴いてもらおうという意味でお賽銭をしている ...
-

-
参拝(さんぱい)- 寺院へのお参りについて
参拝とは、敬意を表してうやうやしく寺院などの本尊に手を合わせ、頭を下げて祈ることです。その寺院に複数のお堂がある場合、まずは本堂の本尊にお参りし、他のお堂に行く機会があればそれぞれのお堂 ...
-

-
三毒(さんどく)
三毒とは、迷い苦しむ原因となる欲望のことで、煩わせる心・悟りに至る道を妨げる心のことで、人間の諸悪・苦しみの根源とされている貪・瞋・癡(とん・じん・ち)のことを指します。その中でも癡が根 ...
-

-
サヘート・マヘート - ブッダ布教の地(祇園精舎・舎衛城)
サヘート・マヘートはブッダ布教の地として仏教の八大聖地の一つに数えられます。隣接した二つの遺跡群をまとめた呼称です。 ①サヘート遺跡・・・祇園精舎(祇園は「祇樹給孤独園」の略。ジェータ林 ...
-
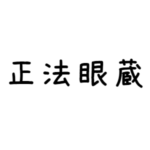
-
「正法眼蔵」三時業(さんじごう)
2020/09/24 -仏教を本気で学ぶ
お釈迦様(ブッダ), さ, アジャータシャトル, サーリプッタ, デーヴァダッタ, モッガラーナ, 仏祖になった人の生き方, 南泉普願, 慧可, 正法眼蔵, 生あるものに利益を与えることを行う, 自分の考えを改めるべき場面, 長沙景岑, 闍夜多, 阿逸多, 鳩摩羅多この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
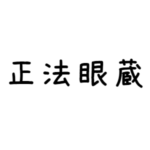
-
「正法眼蔵」三時業(さんじごう)/六十巻本
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-
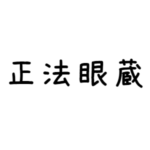
-
「正法眼蔵」坐禅箴(ざぜんしん)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
三世仏(さんぜぶつ)
三世仏、三世如来とも呼ばれます。過去・現在・未来の三世に対応した仏・如来を指します。代表的なものは上掲載画像のように向かって左から、阿弥陀仏・釈迦仏・弥勒仏を、それぞれ過去・現在・未来の ...
-

-
三蔵法師(さんぞうほうし)
三蔵法師(さんぞうほうし)とは、仏教の経蔵・律蔵・論蔵の三蔵に精通した高僧のことです。また、訳経僧を指していう場合もあります。 日本では中国の小説『西遊記』に登場する人物「三蔵法師」とし ...
-

-
梵語(サンスクリット語・梵字・悉曇)
梵語(ぼんご・サンスクリット語)とは、古代インドの文章語であり、北伝の仏教(説一切有部とその分派、ならびに大乗仏教の諸部派)に使われている言葉です(⇔南伝・巴語)。「サンスクリット」とは ...
-

-
犀の角(さいのつの)
犀の角が一つしかないように、求道者は、他の人々からのほめたりけなしたりする世評に煩わされることなく、ただ一人でも自分の確信に随って暮らすようにという意味が込められている。「犀の角」の譬喩によって「独り ...