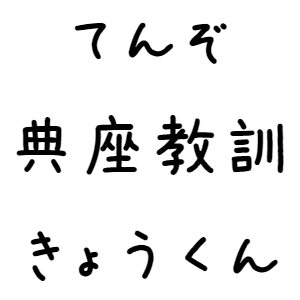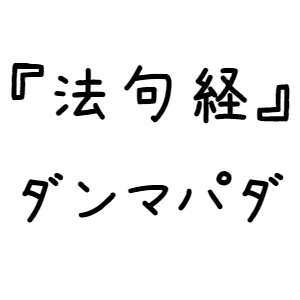仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ スッタニパータ – ブッダの言葉
かの尊き師・尊き人、覚った人に礼したてまつる。【 第1 蛇の章 】1、蛇1 身体に蛇の毒がひろがるのを薬で制するように、怒りが起こったのを制する修行者(比丘)は、この世とかの世とをともに捨て去る。蛇が脱皮してふるい皮を捨て去るように。2 池の蓮華を水にもぐって折り取るように、愛欲を断ってしまった修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る。 蛇が脱皮してふるい皮を捨て去るように。3 流れる妄執の水をからし尽くした修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る。蛇が脱皮してふるい皮を捨て去るように。4 激流が弱々しい葦の橋を壊すように、すっかり驕慢を滅し尽くした修行者は、この世とかの世とをともに捨て去...