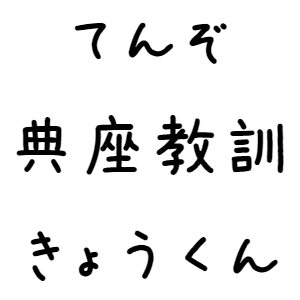人物
人物 小早川隆景(こばやかわたかかげ)
戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。竹原小早川家第14代当主。後に沼田小早川家も継ぐ。 毛利元就の三男で、兄弟に同母兄の毛利隆元・吉川元春などがいる。竹原小早川家を継承し、後に沼田小早川家も継承して両家を統合。吉川元春と共に毛利両川として戦国大名毛利氏の発展に尽くした。毛利水軍の指揮官としても活躍している。豊臣政権下では豊臣秀吉の信任を受け、文禄4年(1595年)に発令された「御掟」五ヶ条と「御掟追加」九ヶ条において秀吉に五大老の一人に任じられた。実子はなく、木下家定の五男で豊臣秀吉の養子となっていた羽柴秀俊(小早川秀秋)を養子として迎え、家督を譲っている。特に豊臣秀吉の信頼は厚く、...