「 お 」 一覧
-
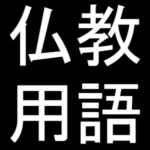
-
仏教用語/人物集 索引
2024/06/13 -仏教を本気で学ぶ
あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, さ, し, す, せ, そ, た, ち, つ, て, と, な, に, ぬ, ね, の, は, ひ, ふ, へ, ほ, ま, み, む, め, も, や, ゆ, よ, ら, り, る, れ, ろ, わ, んこのウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。
-
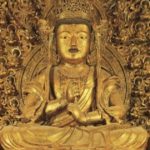
-
億劫(おっくう/おっこう)
億劫とは、一般的にめんどうで気が進まないさまを表します。例えば寒い日に「布団から出るのも億劫だ」と使われます。 また、仏教では「おっこう」と読み、一劫(いっこう)の億倍を表す言葉です。「 ...
-

-
お彼岸とは?お彼岸は日本独自の文化?
日本の古くからの風習では、ご先祖さまがいると考えられている世界(あの世、極楽、等々)を仏教的な考え方も加わり「彼岸(ひがん)」、いま私たちが生きているこの世界を「此岸(しがん)」といいます。「彼岸」と ...
-

-
魂入れ法要(開眼法要・お性根入れ)
魂入れ法要とは、「たましいいれ」「たまいれ」と読み、仏壇の中に安置するご本尊や位牌、法名軸、または、墓石に魂を入れる儀式であり、開眼法要(かいげんほうよう)、お性根入れ(おしょうねいれ)、入魂式(にゅ ...
-

-
抜魂供養(魂抜き、お性根抜き、閉眼供養)
抜魂供養とは、「ばっこんくよう」と読み、仏壇の中に安置されていたご本尊や位牌、法名軸、または、墓石に宿った魂を抜くための供養です。魂抜き(たまぬき)、お性根抜き(おしょうねぬき)、閉眼供養(へいげんく ...
-

-
オショウライ(御精来・御精霊・御招来)/富山県のお盆の迎え火
(上市川の河川敷に並ぶ「におとんぼ」) 2022年、3年ぶりに上市の花火大会が開催され「オショウライ」「におとんぼ」との共演が見られました。2020年、2021年は上市の花火大会も新型コロナウイルスの ...
-

-
お盆(盂蘭盆会)
お盆(ぼん)、盂蘭盆会(うらぼんえ)とは 日本で夏に行われるの祖先の霊を祀る行事です。日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した特色があります。現在、太陽暦の8月15日を中心とした期間に行われる(旧盆、月遅れ ...
-
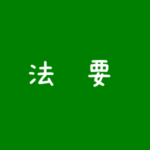
-
オンライン法要(おんらいんほうよう)
オンライン法要とは、インターネットを通じたオンラインで法事や葬儀などの法要を行なうことです。ZOOMやLINE、スカイプなどビデオ通話・ビデオ会議機能を用いて同時進行する場合と、YouT ...
-

-
鬼(おに)- 仏教に関する鬼まとめ
このページでは、仏教に関する鬼についてまとめています。新たなものが更新されると追記していきます。 ・八部鬼衆(はちぶきしゅう)四天王に仕え仏法を守護する8種族の鬼神です。 ・邪鬼(じゃき ...
-

-
踊り念仏(おどりねんぶつ)
念仏や和讃(わさん・仏教歌謡)をとなえ、鉦(かね)・太鼓(たいこ)などを打ち鳴らしながら歓喜(かんき)の状態になる踊り。平安時代に空也(こうや)が民衆にすすめたのに始まり、鎌倉時代に一遍 ...
-
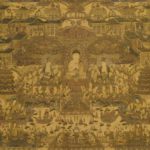
-
往生(おうじょう)
往生とは、この世を去り、極楽浄土に往(い)って生まれることです。日常的には「亡くなる」や「困る」ことをさして使われています。 「大往生」「立ち往生」「往生しまっせ」「往生要集」 往生の意 ...
-
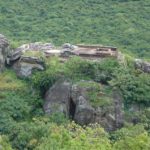
-
ラージギル - ブッダ布教の地(王舎城)
ラージギルはブッダ布教の地として仏教の八大聖地の一つに数えられます。この一帯にはマガダ国の首都・王舎城(おうしゃじょう/ラージャグリハ)、仏教史上最初の寺院と考えられる竹林精舎(ちくりん ...
-

-
鬼瓦(おにがわら)
鬼瓦とは、寺院の諸堂や山門などの瓦葺き建造物の屋根の端などに設置され飾られる瓦を総称してそう呼んでいます。飛鳥時代や白鳳時代の鬼瓦はまだ鬼面ではなく、蓮華文を飾っていましたが、それでも鬼 ...
-
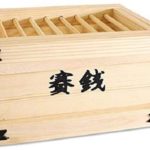
-
お賽銭(おさいせん)
お賽銭とは、お寺や神社にお参りに行った時に、賽銭箱などへお金を入れることです。ただし、2つの意味があります。一般参拝客にとっては、自分のお願いを聴いてもらおうという意味でお賽銭をしている ...
-

-
お線香(おせんこう)- あげ方、由来、宗派による違い
お線香とは、香を焚くための仏具のことで、寺院や家で日常的に使われる他、法事や法要を行なう際、線香に火をつけて香炉に立てて、あるいは寝かせて使います。お線香により自身の匂いを法要に相応しい ...
-

-
お斎(おとき)
お斎とは、一般の方の法事・法要の後、施主が僧侶や参列者を招待して行なう会食のことを指します。お坊さんや参列者に対する感謝を表す場であり、参列者全員で故人の思い出を話す機会でもあります。お ...
-
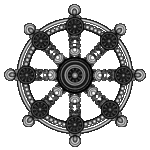
-
お布施(おふせ)
一般的に理解されているお布施とは、法要の際に寺院に渡す金品のことを指しています。お布施の金額は前もって分かっていた方が良いと思いますが、実際のところ、地域や宗派によって金額が異なる、もしくは、家の格や ...
-

-
織田無道(おだむどう)
2020/12/09 -人物
08月08日, 12月09日, 2020年, お, 円光寺-神奈川県厚木市, 織田無道, (命日)12月09日, (生誕)08月08日僧侶、タレント。神奈川県厚木市出身で自称織田信長の子孫。臨済宗建長寺派円光禅寺の第49代住職。 生誕 1952年(昭和27年)8月8日 命日 2020年(令和2年)12月9日 << 戻る
-

-
施餓鬼会(せがきえ)- おせがき
施餓鬼会とは、施餓鬼、施食会(せじきえ)とも呼ばれる寺院で行われる法会の名称です。修める時期に定めはありませんが、多くの地域・宗派では7月や8月のお盆前後に勤められており、この場合はとく ...
-

-
お焼香(おしょうこう)- 作法
お焼香とは、香を焚くことで、一般的にはお通夜やお葬式、法事などの法要会場に設置された焼香台で行います。お焼香により自身の匂いを法要に相応しい香りにし、この香りがする時には亡き人を思い出す ...
-
-150x150.jpg)
-
厭離穢土(おんりえど)
厭離穢土とは、この世をけがれた世界として厭(いと)い離れることです。 源信の『往生要集』には、大文第一を厭離穢土、第二を欣求浄土(ごんぐじょうど)とし、この思想を浄土信仰の基本としていま ...
-

-
お婆ちゃんのお経
お寺の手伝いを始めたばかりのお寺の息子が、お盆やお彼岸、月参りなどで檀家や門徒の家にお参りに行くと、その家のお婆ちゃんの方がお経が上手く、お寺の息子はうろたえてしまうということがあります ...
-

-
寺院・お寺
寺院・お寺とは、仏教の活動拠点となる建物およびその所在する境内(けいだい)をいいます。精舎(しょうじゃ)、僧伽藍(そうぎゃらん)、伽藍(がらん))、仏刹(ぶっさつ)などとも呼ばれます。イ ...
-

-
思い上がることのない者
自分が他人より優れていると思う慢心がない人のこと。または、家柄や家筋、生まれや家系、経歴といったことについて、自分の方が優れていると思って他人を見下すことがない人のこと。 ・「究極の理想に通じた人が、 ...
-

-
岡江久美子(おかえくみこ)
2020/04/23 -人物
04月23日, 08月23日, 2020年, お, (命日)04月23日, (生誕)08月23日女優、タレント、司会者。主な作品・テレビドラマ『天までとどけ』『七人の女弁護士』『終着駅シリーズ』『密会の宿』(テレビ東京版)、『ラッキーセブン』、情報・教養番組 『連想ゲーム』『はなま ...
-

-
お寺ヨガ
「お寺でヨガやってるよ」 と聞くと、檀家さんを対象とした催しか、新たな人をお寺に呼びたいための催しか、だいたいこの2通りです。私たち一般人にとっては、ヨガがやりたいのであれば宗派・宗旨なんてどうでもい ...
-

-
大橋巨泉(おおはしきょせん)
2016/07/12 -人物
03月22日, 07月12日, 2016年, お, 戒名, (命日)07月12日, (生誕)03月22日テレビタレント、放送作家、政治家。 テレビ司会者のほか、競馬評論家、ジャズ評論家、時事評論家としての活動も行い、馬主でもあるなど、日本のマルチタレントの先駆けとなった。 生誕 1934年 ...
-

-
大塚周夫(おおつかちかお)
2015/01/15 -人物
01月15日, 07月05日, 2015年, お, (命日)01月15日, (生誕)07月05日声優、俳優、ナレーター。 劇団東芸、劇団俳優小劇場、芸能座などで活動し、最後は青二プロダクションに所属していた。 生誕 1929年7月5日 命日 2015年1月15日 << 戻る
-

-
大瀧詠一(大滝詠一/おおたきえいいち)
2013/12/30 -人物
07月28日, 12月30日, 2013年, お, (命日)12月30日, (生誕)07月28日ミュージシャン。 シンガーソングライター、作曲家、アレンジャー、音楽プロデューサー、レコードレーベルのオーナー、ラジオDJ、レコーディング・エンジニア、マスタリング・エンジニア、著述家、 ...
-

-
大島渚(おおしまなぎさ)
2013/01/15 -人物
01月15日, 03月31日, 2013年, お, 回春院-神奈川県鎌倉市, 戒名, 築地本願寺-東京都中央区, (命日)01月15日, (生誕)03月31日映画監督、脚本家、演出家、著述家。フィクションだけでなくドキュメンタリーも制作した。京都大卒業後の54年、松竹大船撮影所に入所し、59年「愛と希望の街」で監督デビュー。83年に「戦場のメ ...
-

-
小沢昭一(おざわしょういち)
2012/12/10 -人物
04月06日, 12月10日, 2012年, お, 戒名, (命日)12月10日, (生誕)04月06日俳優、タレント、俳人、エッセイスト、芸能研究者、元放送大学客員教授。日本新劇俳優協会会長。俳号は小沢 変哲。劇団「しゃぼん玉座」主宰。見世物学会顧問。 生誕 1929年(昭和4年)4月6 ...
-

-
大滝秀治(おおたきひでじ)
2012/10/02 -人物
06月06日, 10月02日, 2012年, お, 戒名, (命日)10月02日, (生誕)06月06日俳優、ナレーター、実業家。文化功労者。株式会社劇団民藝代表取締役などを歴任した。 生誕 1925年(大正14年)6月6日 命日 2012年(平成24年)10月2日 瑞藝院秀聲居士 << ...