「 い 」 一覧
-
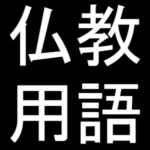
-
仏教用語/人物集 索引
2024/06/13 -仏教を本気で学ぶ
あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, さ, し, す, せ, そ, た, ち, つ, て, と, な, に, ぬ, ね, の, は, ひ, ふ, へ, ほ, ま, み, む, め, も, や, ゆ, よ, ら, り, る, れ, ろ, わ, んこのウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。
-

-
今くるよ(いまくるよ)
2024/05/27 -人物
05月27日, 06月17日, 2024年, い, (命日)05月27日, (生誕)06月17日高校の同級生コンビで結成された今いくよ・くるよで活躍した漫才師。所属事務所は吉本興業。派手な色柄やフリルのついた衣装は専属のデザイナーがついていた。腹を叩いたり、両手を顔の前で交互に前後 ...
-

-
十二因縁(じゅうにいんねん)
十二因縁とは、人間の苦しみ、悩みがいかにして成立するかということを考察し、その原因を追究して十二の項目(無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死)の系列を立てたものです。 存在の基本的構 ...
-

-
生きとし生けるもの
人間ばかりでなく、生きもの全てを対象としている。 ・「一切の生きとし生けるものは、幸福であれ、安穏であれ、安楽であれ。」(スッタニパータ 145偈) << 戻る
-
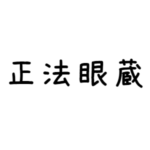
-
「正法眼蔵」一百八法明門(いっぴゃくはちほうみょうもん)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
韋駄天(いだてん)
韋駄天は、韋駄尊天などとも呼ばれ、インドでヒンドゥーの軍神であるスカンダが仏教に取り入れられて、仏法の護法神となり成立したと考えられています。中国に入って道教の韋将軍信仰と習合したことか ...
-

-
一度生まれるもの
一度生まれるもの(ekaja)とは、胎生の動物のこと。 ・「一度生まれるものでも、二度生まれるものでも、この世で生きものを害し、生きものに対するあわれみのない人、彼を賤しい人であると知れ。」(スッタニ ...
-
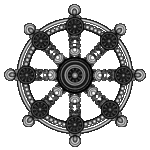
-
インドラケートゥ・ドバージャ・ラージャ
2020/09/10 -仏教を本気で学ぶ
い, インドラケートゥ・ドバージャ・ラージャインドラケートゥ・ドバージャ・ラージャとは、帝釈天の幢幡<はたぼこ>の王という意味の上方の現在仏です。漢訳仏典には翻訳されなかったので漢字の名前はありません。梵語では indraketu ...
-

-
板橋興宗(いたばしこうしゅう)
2020/07/05 -人物, 仏教を本気で学ぶ, 年表
05月20日, 07月05日, 2020年, い, 御誕生寺-福井県越前市, 曹洞宗, 曹洞宗の出来事, 總持寺-神奈川県横浜市鶴見区, 總持寺祖院-石川県輪島市, (命日)07月05日, (生誕)05月20日曹洞宗の僧侶。閑月即眞禅師。大本山總持寺独住23世(貫首)。曹洞宗管長、總持寺祖院住職、大乗寺山主、御誕生寺住職を歴任。宮城県多賀城市出身。 1927年(昭和2年)、宮城県多賀城市の農家 ...
-
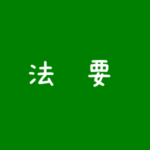
-
一周忌法要(いっしゅうき)
一周忌とは、お亡くなりになってから1年後、同じ月、同じ日の祥月命日に行う法要です。様々な都合により、現在では祥月命日に行えないことも多くなっています。 無料や有料の法要依頼 当ウェブサイトから行える法 ...
-
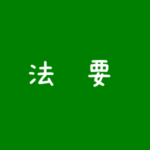
-
五七日(いつなのか)- 小練忌
五七日のことを小練忌(しょうれんき)とも言います。亡くなられた日から数えて35日目に行なわれます。また、関西ではお逮夜を重視して34日目にする場合があります。 五七日の本尊・地蔵菩薩に苦しみを解いても ...
-

-
四向四果(しこうしか)
四向四果とは、初期の仏教での聖者の位を、預流(よる)、一来(いちらい)、不還(ふげん)、阿羅漢(あらかん)という四つの聖位に分けられており(四双/しそう)、その一つ一つの位について向と果がありました。 ...
-

-
井上洋介(いのうえようすけ)
2016/02/03 -人物
02月03日, 03月07日, 2016年, い, (命日)02月03日, (生誕)03月07日絵画・版画美術家、日本の絵本作家、イラストレーター。東京府出身。武蔵野美術学校西洋画科卒。1960年「こどものとも」で初の絵本「おだんごぱん」刊行。以後、多数創作絵本出版。1965年第1 ...
-

-
今いくよ(いまいくよ)
2015/05/28 -人物
05月28日, 12月03日, 2015年, い, 戒名, (命日)05月28日, (生誕)12月03日高校の同級生コンビで結成された今いくよ・くるよで活躍した漫才師。所属事務所は吉本興業。痩せすぎているほど細い体型や厚化粧が特徴。長すぎる睫毛で、パチパチ瞬きをしたり首筋を掻く仕草をよくし ...
-

-
今井雅之(いまいまさゆき)
2015/05/28 -人物
04月21日, 05月28日, 2015年, い, 戒名, (命日)05月28日, (生誕)04月21日俳優・演出家・脚本家・タレント・エッセイスト。兵庫県城崎郡日高町出身。代表作は自身が「自分の魂」と形容している神風特別攻撃隊が主題の演劇・映画『THE WINDS OF GOD』や、自身 ...
-

-
岩谷時子(いわたにときこ)
2013/10/25 -人物
03月28日, 10月25日, 2013年, い, 戒名, (命日)10月25日, (生誕)03月28日作詞家、詩人、翻訳家。歌手・越路吹雪のマネージャーを務めました。 生誕 1916年(大正5年)3月28日 命日 2013年(平成25年)10月25日 詞玉院超世時空大姉 << 戻る
-

-
飯野賢治(いいのけんじ)
2013/02/20 -人物
02月20日, 05月05日, 2013年, い, (命日)02月20日, (生誕)05月05日ゲームクリエイター、実業家。 有限会社EIM、株式会社ワープ、株式会社スーパーワープ、株式会社フロムイエロートゥオレンジなどで代表取締役社長を務めた。著名な実績『Dの食卓』『エネミー・ゼ ...
-

-
伊良部秀輝(いらぶひでき)
2011/07/27 -人物
05月05日, 07月27日, 2011年, い, (命日)07月27日, (生誕)05月05日兵庫県尼崎市出身の元プロ野球選手。右投右打。1987年から日本&メジャーの両リーグで活躍した。 生誕 1969年5月5日 命日 2011年7月27日 << 戻る
-

-
身・口・意の三業(さんごう)
食べる、寝る、座る、立つ、歩く、走る。身体で表すどんな動きも自分以外のものに影響を与えています。また、自分以外のものや環境から影響を受けて自分の身体が動いています。言葉で表すどんなことも正しく伝わって ...
-

-
石井好子(いしいよしこ)
2010/07/17 -人物
07月17日, 08月04日, 2010年, い, 戒名, (命日)07月17日, (生誕)08月04日シャンソン歌手、エッセイスト、実業家(芸能プロモーター)。日本シャンソン界の草分けであり、半世紀以上に亘り牽引し続けた業界の代表・中心人物として知られている。日本シャンソン協会初代会長。 ...
-

-
井上ひさし(いのうえひさし)
2010/04/09 -人物
04月09日, 11月16日, 2010年, い, 戒名, (命日)04月09日, (生誕)11月16日小説家、劇作家、放送作家である。文化功労者、日本藝術院会員。本名は井上 廈。1961年から1986年までの本名は内山 廈。遅筆堂を名乗ることもあった。 日本劇作家協会理事、社団法人日本文 ...
-

-
忌野清志郎(いまわのきよしろう)
2009/05/02 -人物
04月02日, 05月02日, 2009年, い, 戒名, (命日)05月02日, (生誕)04月02日ロックミュージシャン。RCサクセションを筆頭に、忌野清志郎 & 2・3'S、忌野清志郎 Little Screaming Revue、ラフィータフィーなどのバンドを率い、ソウル・ブルース ...
-

-
飯島愛(いいじまあい)
2008/12/17 -人物
10月31日, 12月17日, 2008年, い, 戒名, (命日)12月17日, (生誕)10月31日元AV女優、タレント。『プラトニック・セックス』 生誕 1972年10月31日 命日 2008年12月17日 寛愛翠松大姉 << 戻る
-

-
井沢八郎(いざわはちろう)
2007/01/17 -人物
01月17日, 03月18日, 2007年, い, (命日)01月17日, (生誕)03月18日演歌歌手。代表曲は『あゝ上野駅』。 生誕 1937年3月18日 命日 2007年1月17日 << 戻る
-

-
伊福部昭(いふくべあきら)
2006/02/08 -人物
02月08日, 05月31日, 2006年, い, (命日)02月08日, (生誕)05月31日作曲家。ほぼ独学で作曲家となった。日本の民族性を追求した民族主義的な力強さが特徴の数多くの管弦楽作品や、『ゴジラ』を初めとする映画音楽のほか、音楽教育者としても知られる。 伊福部家は大己 ...
-

-
いかりや長介(いかりやちょうすけ)
2004/03/20 -人物
03月20日, 11月01日, 2004年, い, 戒名, (命日)03月20日, (生誕)11月01日男性コメディアン、ミュージシャン(ベーシスト)。 「ザ・ドリフターズ」(略称:ドリフ)の3代目リーダー。 生誕 1931年11月1日 命日 2004年3月20日 瑞雲院法道日長居士 << ...
-

-
伊東一雄(いとうかずお)- パンチョ伊東
2002/07/04 -人物
04月07日, 07月04日, 2002年, い, (命日)07月04日, (生誕)04月07日は、日本の野球解説者、メジャーリーグ評論家。 「パンチョ伊東」の愛称・通称で広く知られた。球界きってのメジャー通で知られ、野茂英雄やイチローら多くの日本人メジャーリーガーが慣れない異国の ...
-
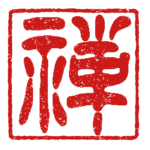
-
維那(いのう/いな)
維那とは、修行僧の監督、修行道場内の庶務を担います。六知事の一つ。 ・「念誦の法は、大衆集定ののち、住持人まづ焼香す。つぎに知事、頭首、焼香す。浴仏のときの焼香の法のごとし。つぎに維那、くらゐより正面 ...
-

-
ブッダ最後の旅【 第6章 】25、遺体の火葬
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
ブッダ最後の旅【 第6章 】26、遺骨の分配と崇拝
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
ブッダ最後の旅【 第3章 】10、命を捨てる決意
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
-

-
ブッダ最後の旅【 第4章 】14、一生の回顧 - バンダ村へ
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。