 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 漢讃(かんさん)
漢讃とは、仏教歌謡・声明の一種で、仏・菩薩の功徳や仏法をたたえ、祖師・先人の徳、経典・教義などに対して漢文(韻文)を使ってほめたたえる讃歌です。漢語讃。多くは梵讃の漢訳であることが多いようです。また、中国・朝鮮・日本などにおいて、漢文でつづった仏教の讃歌のことをいいます。<< 戻る
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 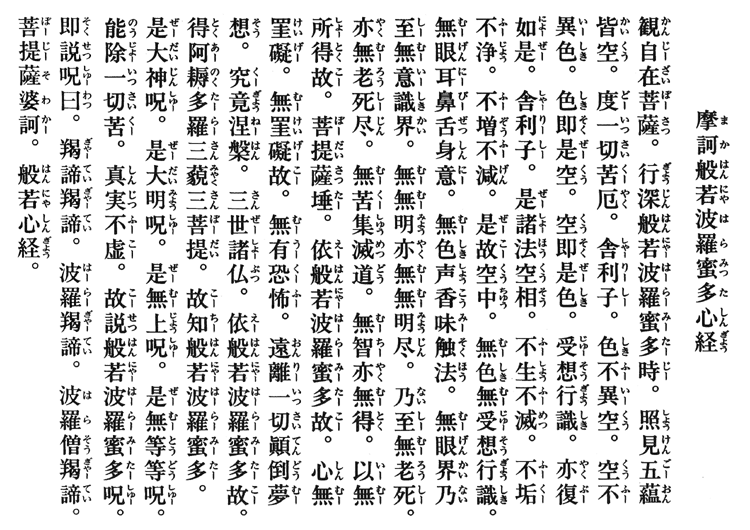 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 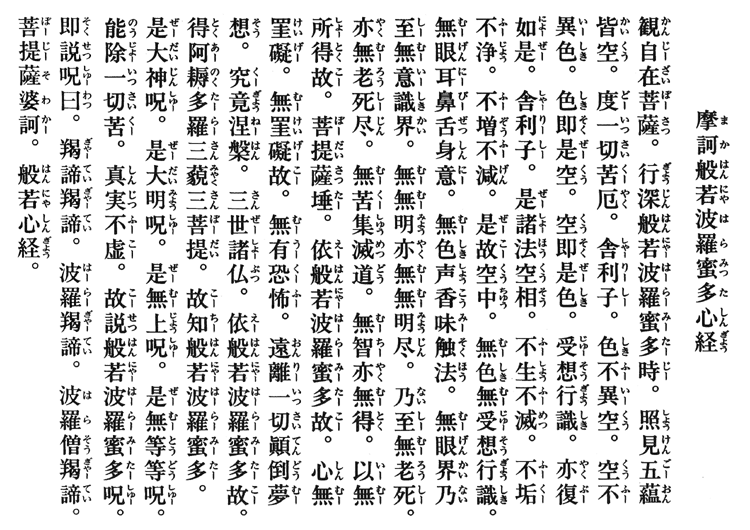 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ  仏教を学ぶ
仏教を学ぶ