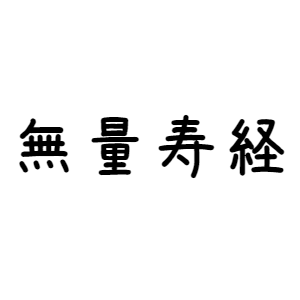無量寿経は紀元後100年頃にインド文化圏で成立したと考えられている大乗仏教の経典です。もともとの梵語(サンスクリット語)では सूखावतीव्यूह, Sukhavati-vyuha, スカーヴァティー・ヴィユーハ(極楽の荘厳、幸あるところの美しい風景)となります。同タイトルの『阿弥陀経』と区別して『大スカーヴァティー・ヴィユーハ』とも呼ばれます。略称は、『阿弥陀経』の『小経』に対して、無量寿経を『大経』とも呼んでいます。
①ルビ(かな読み)
②漢訳本文(大太字)
③講話
人物や単語の解説が必要な場合はその言葉のリンク先を参照下さい。各宗派や時代によりお経の解釈は違うものです、当ウェブサイトの一解釈としてご覧ください。
なお、短く区切っているのはスマホ対応の為です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぶっせつむりょうじゅきょう
仏説無量寿経
そうぎてんじくさんぞうこうそうがいやく
曹魏天竺三蔵康僧鎧訳
にょぜがもん、いちじぶつ、
我聞如是、一時仏、
じゅうおうしゃじょう、
住王舎城、
ぎしゃくっせんちゅう、
耆闍崛山中、
よだいびくしゅう、まんにせんにんく。
与大比丘衆、万二千人倶。
いっさいだいじょう、じんつういだつ。
一切大聖、神通已達。
きみょうわつ、そんじゃりょうほんざい、
其名曰、尊者了本際、
そんじゃしょうがん、そんじゃしょうご、
尊者正願、尊者正語、
そんじゃだいごう、そんじゃにんげん、
尊者大号、尊者仁賢、
そんじゃりく、そんじゃみょうもん、
尊者離垢、尊者名聞、
そんじゃぜんじつ、そんじゃぐそく、
尊者善実、尊者具足、
そんじゃごおう、
尊者牛王、
そんじゃうるびんらかしょう、
尊者優楼頻螺迦葉、
そんじゃがやかしょう、
尊者伽耶迦葉、
そんじゃなだいかしょう、
尊者那提迦葉、
そんじゃまかかしょう、
尊者摩訶迦葉、
そんじゃしゃりほつ、
尊者舎利弗、
そんじゃだいもくけんれん
尊者大目犍連、
そんじゃこうひんな、そんじゃだいじゅう
尊者劫賓那、尊者大住、
そんじゃだいじょうし、
尊者大浄志、
そんじゃまかしゅな、
尊者摩訶周那、
そんじゃまんがんし、そんじゃりしょう、
尊者満願子、尊者離障、
そんじゃるかん、そんじゃけんぶく、
尊者流灌、尊者堅伏、
そんじゃめんのう、そんじゃいじょう、
尊者面王、尊者異乗、
そんじゃにんしょう、そんじゃからく、
尊者仁性、尊者嘉楽、
そんじゃぜんらい、そんじゃらうん、
尊者善来、尊者羅云、
そんじゃあなん。
尊者阿難。
かいみょうしとう、じょうしゅしゃや。
皆如斯等、上首者也。
▼ 講話
お経のタイトルに「仏説」と付いているものは、お釈迦様の説いたお経という設定になっています。この無量寿経もお釈迦様が説いている姿をイメージしながら聞くと良いと思います。
曹魏の時代とあるので、中国の三国志の時代に漢訳されたお経ですね。誰が漢訳したかも書かれていて康僧鎧(こうそうがい)というお坊さんです。天竺、つまりインド出身の僧とここに書かれているわけですが、康の字から西域の「康国/康居国」の出身とする説もあるようです。昔の話ですからはっきりしないことも多いのです。
「如是我聞」というのは「私はこのように聞いた」という意味です。ある時、お釈迦様から聞いた話をここでしますという書き出しです。
お釈迦様が王舎城、現在でいうところのラージギルの霊鷲山に修行僧の仲間と共に滞在していたと、ここで「万二千人」と出てきますが、梵語の原典を見ると「3万2千人」の修行僧と出て来るので、このような内容だったのでしょう。
どのような修行僧たちがいたかというと、うやまわれるべき人たちで、汚れは尽き、煩悩は無くなり、修行を完成し、正しい知識によって心がよく解脱し、迷いの生存への多くの束縛が無く、自分が生きていることの意義を達成していて、自分に打ち勝ち、最上の修練を行ない、静かな状態に到達し、心がのびのびとして、捕らわれの無い叡智を持ち、大いなる象であり、六つの神通力によって自由自在であり、心を解放する八つの精神統一に思いをひそめ、力を得、神通に達し、長老であり、偉大な弟子たちであったと漢訳にはない部分も原典にはあります。
次にそのお釈迦様の弟子たちの内、代表的な方々が紹介されています。尊者了本際(阿若憍陳如)、尊者正願(馬勝)、尊者正語(バーシパ)、尊者大号(マハーナーマン)、尊者仁賢(パドラジット)、尊者離垢(ヴィマラ)、尊者名聞(ヤショーデーヴァ)、尊者善実(スバーフ)、尊者具足(プールナ)、尊者牛王(憍梵波提)、尊者優楼頻螺迦葉(ウルヴィルヴァー・カーシャパ)、尊者伽耶迦葉(ガヤー・カーシャパ)、尊者那提迦葉(ナディー・カーシャパ)、尊者摩訶迦葉、尊者舎利弗、尊者大目犍連、尊者劫賓那、尊者大住、尊者大浄志、尊者摩訶周那、尊者満願子、尊者離障、尊者流灌、尊者堅伏、尊者面王、尊者異乗、尊者仁性、尊者嘉楽、尊者善来(ウヴァーガタ)、尊者羅云、尊者阿難。
これらのお釈迦様の弟子たちは、皆長老であり、偉大な弟子たちだったという紹介で漢訳は丸く収めているのですが、原典では、厳密にお釈迦様が生存中に悟りを開くことが出来なかった阿難については、修行の道において直すところが残っていたとして、1人を除いてみんな立派だったという表現になっています。
※このページは学問的な正確性を追求するものではありません。前知識のない一般の方でも「読んでみよう!」と思ってもらえるよう、より分かりやすく読み進めるために編集しています。漢字をひらがなに、旧字体を新字体に、送り仮名を現代表記に、( )にふりがなをつけるなど、原文に忠実ではない場合があります。
<< 戻る