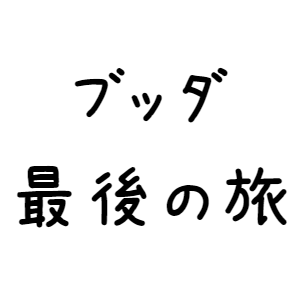仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 弁道(べんどう)
弁道とは、全力をあげて仏道の修行に励むこと、仏道を実践修行することです。また、仏道を信じ、あるいは悟ること、真理の探究という意味もあります。・「専一に功夫せば、正に是れ弁道なり、修証自ら染汚せず、趣向更に是れ平常なるものなり。」(『普勧坐禅儀』)・「かの道得のなかに、むかしも修行し証究す、いまも功夫し弁道す。仏祖の仏祖を功夫して、仏祖の道得を弁肯するとき、この道得、おのづから三年、八年、三十年、四十年の功夫となりて、尽力道得するなり。」(「正法眼蔵」道得)・「又、霊雲志勤禅師は三十年の弁道なり。あるとき遊山するに、山脚に休息して、はるかに人里を望見す。時に春なり。桃花のさかりなるをみて、忽然と...