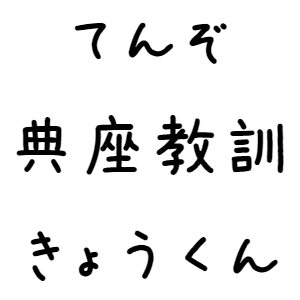人物
人物 立花道雪(たちばなどうせつ)
戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。豊後の戦国大名・大友氏の家臣。臼杵鑑速や吉弘鑑理らと共に大友家の三宿老に数えられた。 大友義鑑・大友義鎮の2代に仕えた大友家の宿将で、北九州各地を転戦し、その勇猛は諸国に知られて恐れられた。本人は立花姓を名乗っておらず、戸次鑑連または戸次道雪で通している。生誕 永正10年3月17日(1513年4月22日)命日 天正13年9月11日(1585年11月2日)福厳院殿前丹州太守梅岳道雪大居士<< 戻る