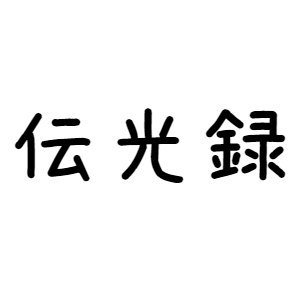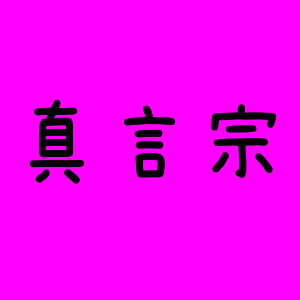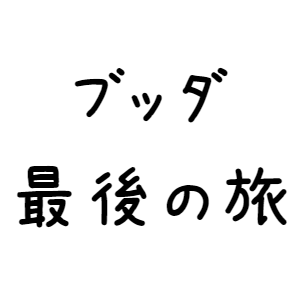人物
人物 はらたいら
男性漫画家、随筆家、タレント。血液型B型。高知県香美郡土佐山田町出身、東京都文京区小石川に居住していた。『クイズダービー』の1976年8月7日放送分にゲスト出場者の一人として出演。翌年の1月22日放送分からは黒鉄ヒロシと交代する形で3枠レギュラーに着任し、番組が終了するまで15年に渡り活躍した。番組出演記録は竹下景子に次いで第2位の記録である。1972年『週刊漫画ゴラク』の連載『モンローちゃん』がヒットする。その後、1980年 サンケイ新聞の『ルートさん』、1988年 北海道新聞や中日新聞、西日本新聞の各夕刊連載の『セロりん』、1981年 - 1983年,1989年 - 1990年 日本経済新...