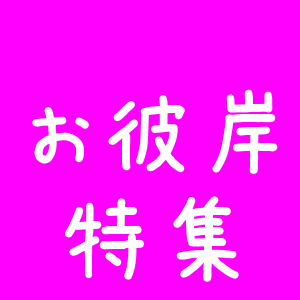 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ お彼岸とは?お彼岸は日本独自の文化?
日本の古くからの風習では、ご先祖さまがいると考えられている世界(あの世、極楽、等々)を仏教的な考え方も加わり「彼岸(ひがん)」、いま私たちが生きているこの世界を「此岸(しがん)」といいます。「彼岸」という言葉は仏教の言葉で、 サンスクリット語の「パーラミター」の漢訳「到彼岸」の略です。「煩悩に満ちた現世である此岸(しがん)を離れて修行を積むことで煩悩を脱し、悟りの境地に達した世界である彼岸に到達する」という意味があります。平安時代、浄土思想が盛んになった頃、真西に沈む太陽を見て、西方極楽浄土を思い描く修行が盛んに行われました。この修行によって極楽浄土に行けると信じられていたことから、3月の春分...

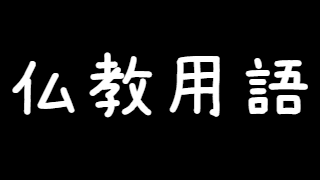





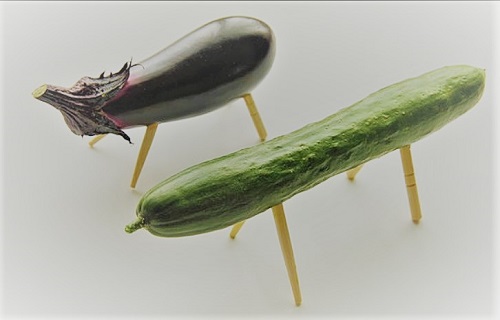

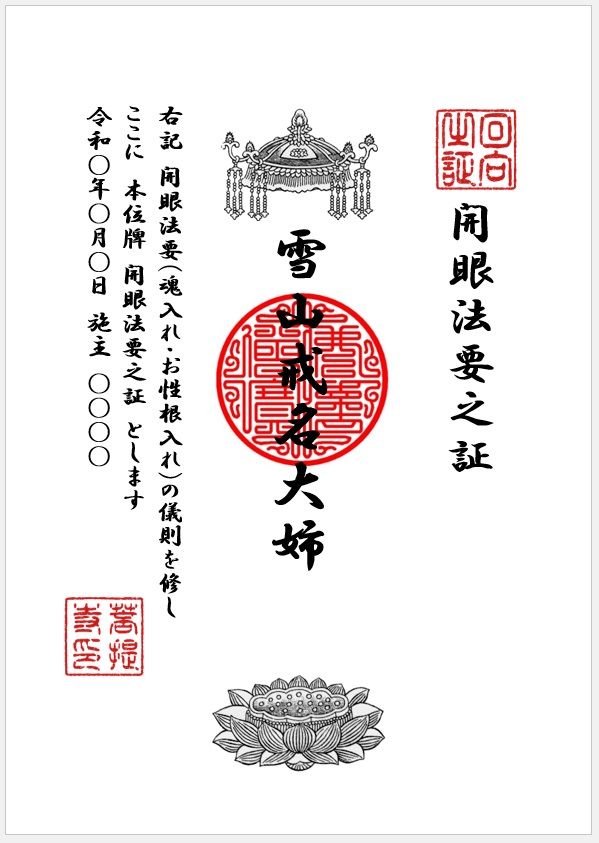

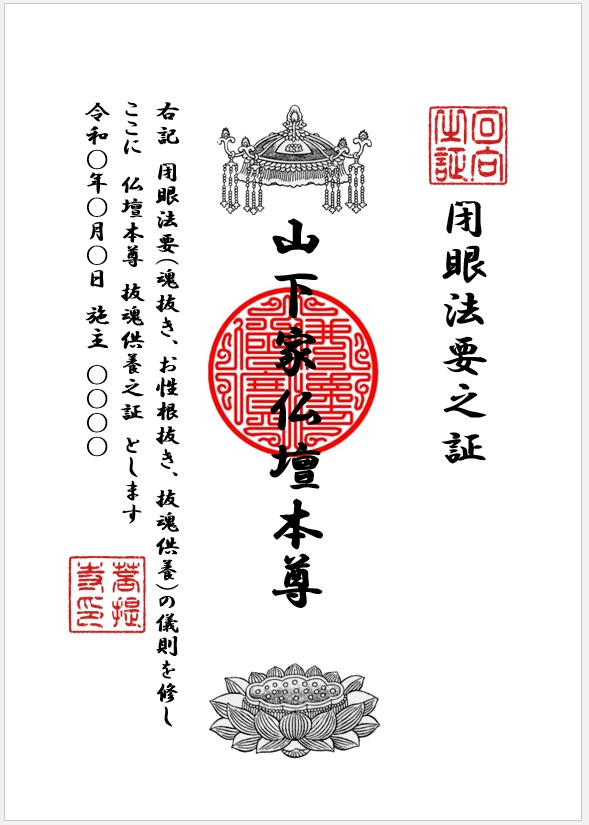





.jpg)
