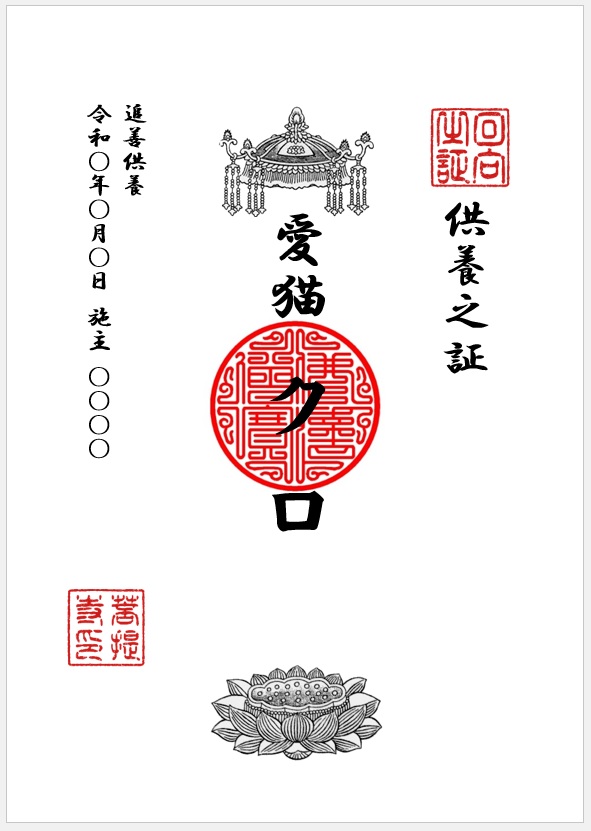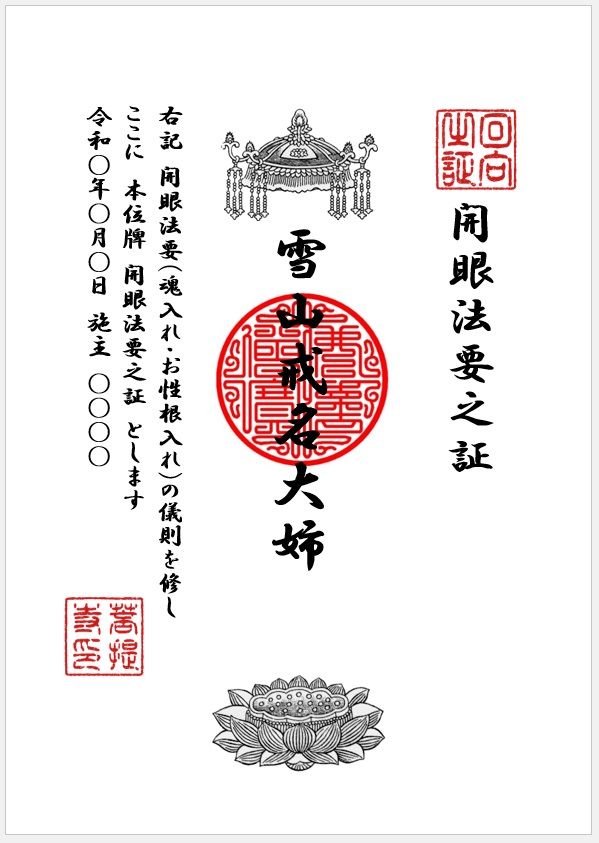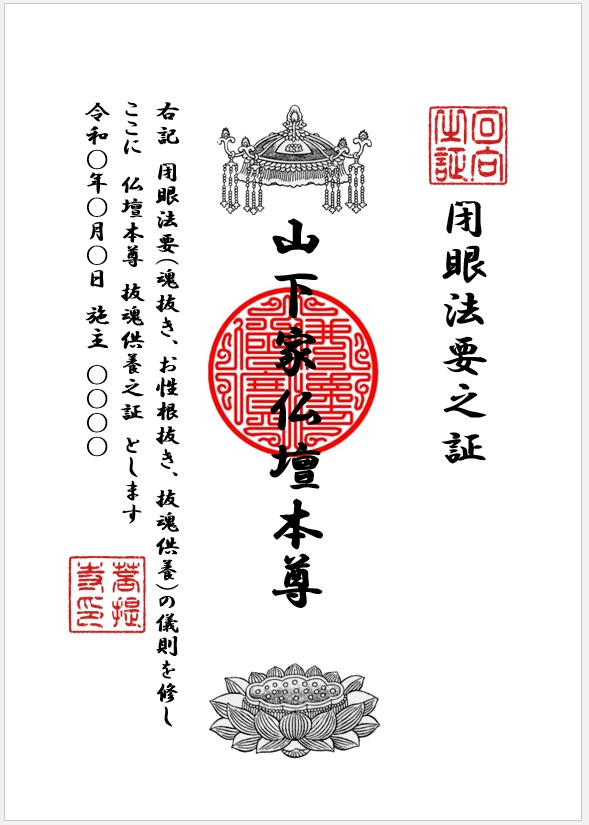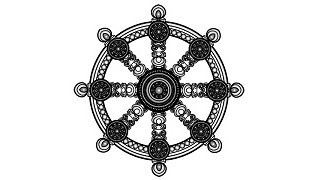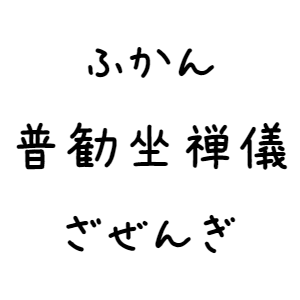仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ キリコ(箱キリコ・板キリコ・風鈴キリコ)/石川県金沢市周辺のお盆
石川県金沢市とその周辺の一部地域では、お盆に墓参りをする時に「キリコ」と呼ばれる木と紙でできた箱型の灯篭のようなものを持参し、中にろうそくを立てて墓前につるす風習があります。類似品として箱キリコ・板キリコ・風鈴キリコ・紙キリコなど様々な形がありますが、他の地域で見られない金沢独自のものです。なお、家庭にもよりますが、石川県内でも「7月盆(新盆)」は金沢市のみで、加賀や能登など石川県のほとんどの地域は「8月盆(旧盆)」で行われる場合が多いです。「キリコ」は先祖の迎え火を保護する為に使われるようになったともいわれますが、その由来に明確な説はないようです。キリコの表面や裏面には持参した人の名前を記入...