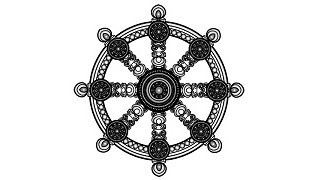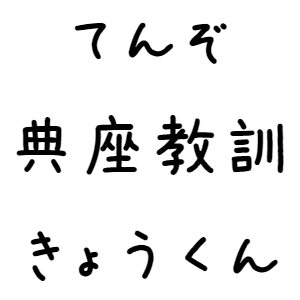仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 涅槃像(ねはんぞう)- クシナガラ
ブッダ入滅の地・クシナガラにある涅槃堂の涅槃像は足のつま先がずれています。これは入滅した(亡くなった)姿を表しているのです。その時80歳、悟りを得た後の45年の伝道の旅を終えた姿です。また、つま先が揃っているものは最後の説法をしている涅槃像です。(2001年撮影)(2017年8月撮影/邪魔な!?フェンスができています)この涅槃像は5世紀のクマラグプタ朝時代にハリバラという信者が寄進したものをマトゥラーからクシナガラへ運んできたものです。この時代、王をはじめとする仏教の信者はクシナガラに僧院や礼拝堂を建て、仏教は保護されていました。涅槃像の足の裏<< 戻る