 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 過去七仏(かこしちぶつ)
過去七仏とは、毘婆尸仏(びばしぶつ)、尸棄仏(しきぶつ)、毘舎浮仏(びしゃふぶつ)、拘留孫仏(くるそんぶつ)、拘那含牟尼仏(くなごんむにぶつ)、迦葉仏(かしょうぶつ)、釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)までの7人のブッダを指します。・七仏通誡偈・第七の仙人<< 戻る
 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物 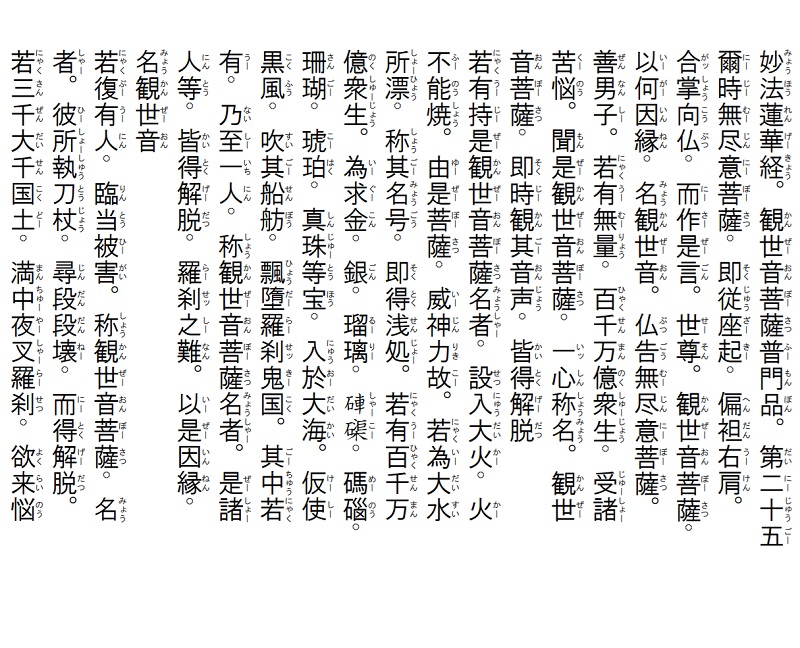 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 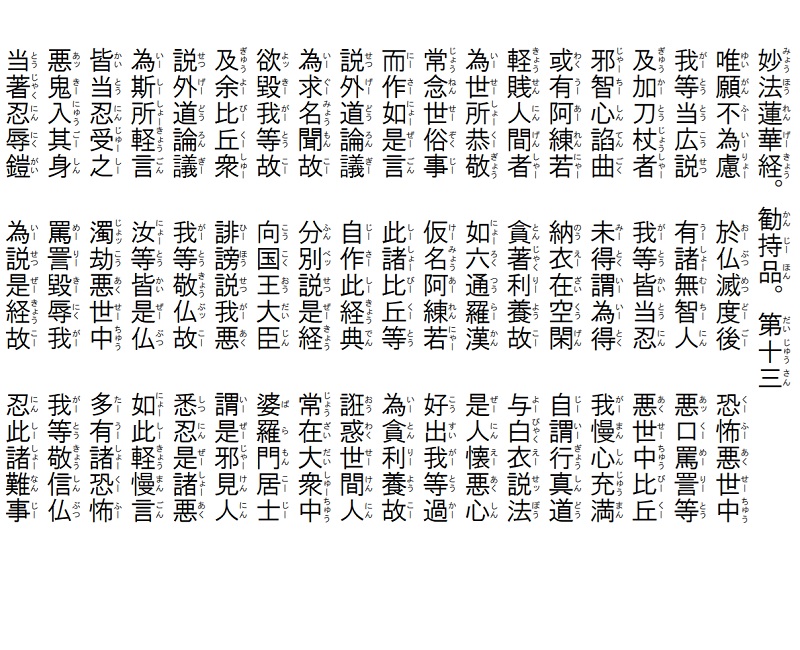 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物 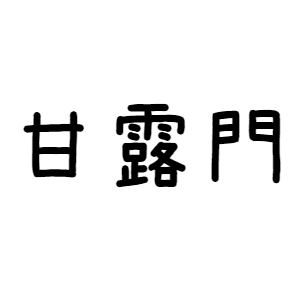 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物 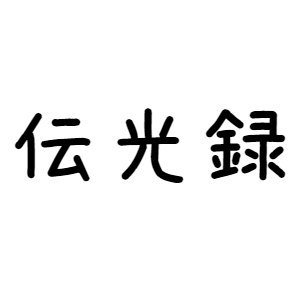 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 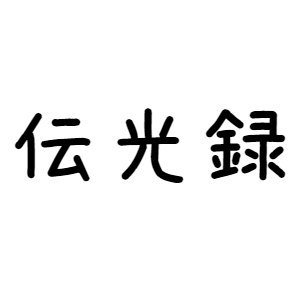 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 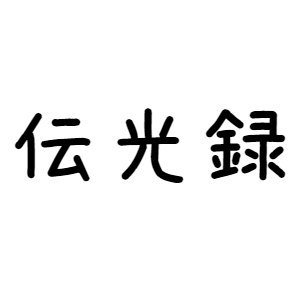 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 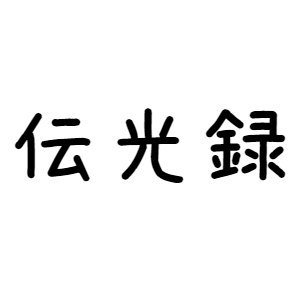 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 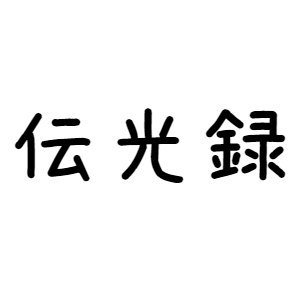 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物 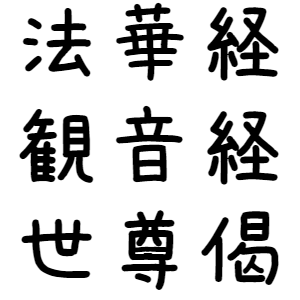 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ