 便り
便り どんな人でも教育を受ける権利がある(曹洞宗 正伝の仏法)
もうひとつ、ボランティア活動でも、戦争、災害などに対する救援活動は目立つんです。税金も出しやすい。しかし、教育というのは緊急性がなくても必要なんです。そういうところには政府もあまりお金を出しません。民間も同じです。そういうのを、我々NGOがやっている、国際貢献、国際援助なんですね。(リンク先より)・どんな人でも教育を受ける権利がある
 便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り 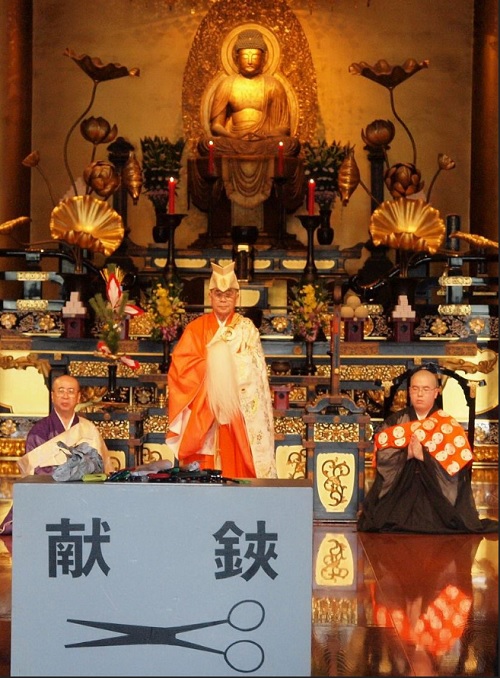 便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り