 人物
人物 井原西鶴(いはらさいかく)
江戸時代の大坂の浮世草子・人形浄瑠璃作者、俳諧師。別号は鶴永、二万翁、西鵬。 『好色一代男』をはじめとする浮世草子の作者として知られる。談林派を代表する俳諧師でもあった。代表作『好色一代男』(1682年)『好色一代女』(1686年)『日本永代蔵』(1688年)『世間胸算用』(1692年)生誕 寛永19年〈1642年〉命日 元禄6年8月10日〈1693年9月9日〉<< 戻る
 人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物 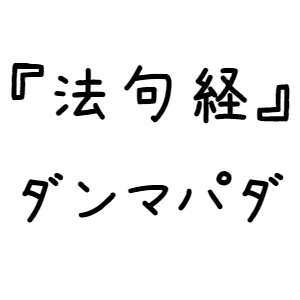 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ