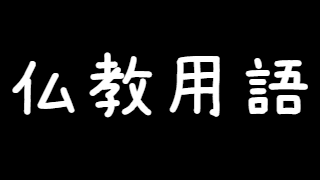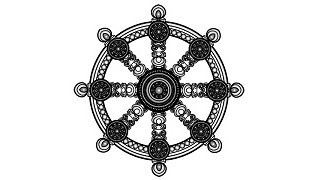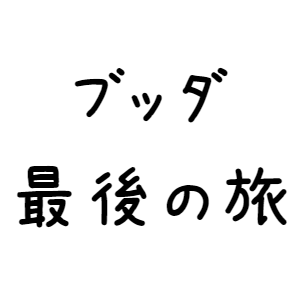仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 身・口・意の三業(さんごう)
食べる、寝る、座る、立つ、歩く、走る。身体で表すどんな動きも自分以外のものに影響を与えています。また、自分以外のものや環境から影響を受けて自分の身体が動いています。言葉で表すどんなことも正しく伝わっているか、伝えたつもりになっていないか注意します。言葉は何かを仮に表したもので、完全なものではありません。心に表れるどんな想い・考えも偏っていないか、その想い・考えに囚われていないか注意します。心に表れたことに囚われると、言葉になり、身体の動きになります。そのような行為のことを業(ごう)といいます。これらの、身体(身)、言葉(口)、心(意)を三業といいます。例えば、地震や大雨などの災害支援ボランティ...