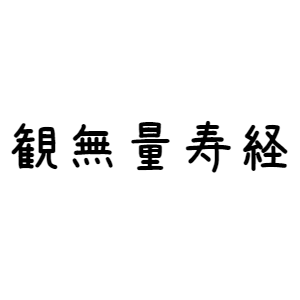観無量寿経は大乗仏教の経典です。別名『観無量寿仏経』、『無量寿仏観経』、『無量寿観経』ともいい、『観経』と略称されます。サンスクリット原典やチベット語訳が発見されていないため、中央アジア撰述説と中国撰述説の二つの説が有力視されています。
①ルビ(かな読み)
②漢訳本文(大太字)
③講話
また、人物や単語の解説が必要な場合はその言葉のリンク先を参照下さい。各宗派や時代によりお経の解釈は違うものです、当ウェブサイトの一解釈としてご覧ください。
なお、短く区切っているのはスマホ対応の為です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぶっせつかんむりょうじゅきょう
仏説観無量寿経
そうげんかちゅきょうりょうやしゃやく
宋元嘉中畺良耶舎訳
にょぜがもん。いちじぶつ、
如是我聞。一時仏、
ざいおうしゃじょう、ぎしゃくつせんじゅ
在王舎城、耆闍崛山中、
よだいびくしゅ、
与大比丘衆、
せんにひゃくごじゅうにんく。
千二百五十人倶。
ぼさつさんまんにせん。
菩薩三万二千。
もんじゅしりほうおうじ、
文殊師利法王子、
にいじょうしゅ。
而為上首。
▼ 講話
こちらのお経のタイトルにも「仏説」と付いているので、お釈迦様が説いたという設定になっているお経だと分かります。
無量寿仏(阿弥陀仏)とその極楽浄土を思い、念ずる対象として観察する方法を説くお経というのが大意です。
観察する人(観行者)は、このお経で説かれていることを自分の心の中に描き出して観察するのですが、観察力が弱いと自覚した人は阿弥陀様の名前を称えることによって、滅罪や見仏、往生の利益を得ることを目的としたお経です。
次に、「宋元嘉中畺良耶舎訳」と書かれている部分は、中国の宋の国の元号である「元嘉中」とあるので、424年~453年の間に漢訳されたことが分かります。漢訳した人の名前が畺良耶舎(きょうりょうやしゃ)とありますが、中央アジア(西域)出身の方です。
「如是我聞」というのは「私はこのように聞いた」という意味ですが、ある時、誰から聞いたかというとお釈迦様です。
王舎城の耆闍崛山中にいたということですが、王舎城というのはラージギルのことです。また、耆闍崛山というのは霊鷲山のことで、お釈迦様がそこに滞在していた時のことが記されています。
そこに1250人もの多くの修行僧たちの集いと共に滞在していたというのは、『阿弥陀経』と同じ人数ですが、さらに、法の王子である文殊菩薩を上首とする32000人の菩薩、求道者と滞在していたということです。
※このページは学問的な正確性を追求するものではありません。前知識のない一般の方でも「読んでみよう!」と思ってもらえるよう、より分かりやすく読み進めるために編集しています。漢字をひらがなに、旧字体を新字体に、送り仮名を現代表記に、( )にふりがなをつけるなど、原文に忠実ではない場合があります。
<< 戻る