 年表
年表 日蓮聖人、仏門へ
天福元(1233)年、父母の元を離れ、生家近くの天台宗清澄寺(後に日蓮宗)の道善房に師事します。薬王丸(やくおうまる)と改名し、四年間仏修行に励みました。そして虚空蔵菩薩に「日本一の智者となしたまへ」と祈願されました。<< 戻る
 年表
年表  便り
便り  人物
人物  便り
便り  年表
年表  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り  年表
年表  便り
便り  便り
便り  人物
人物  便り
便り  便り
便り 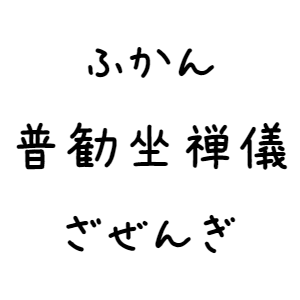 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  年表
年表  人物
人物  人物
人物  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物 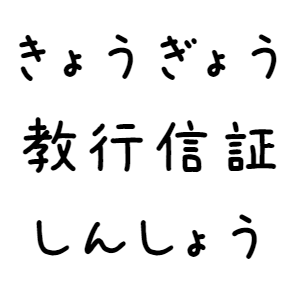 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 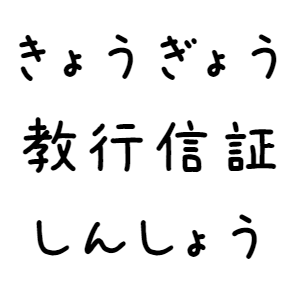 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 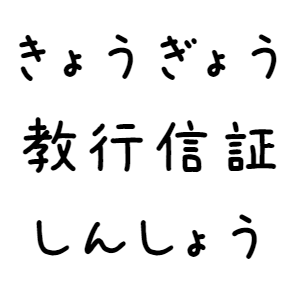 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 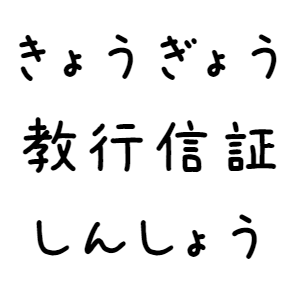 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 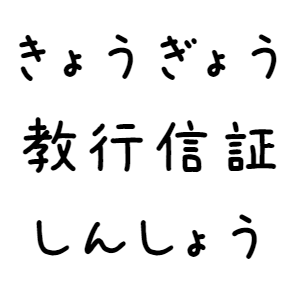 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 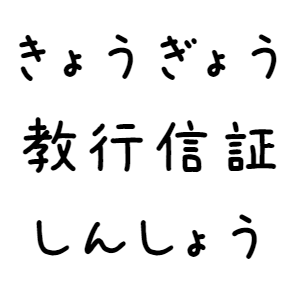 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ