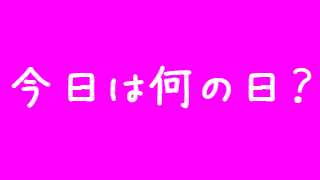 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ buddhism
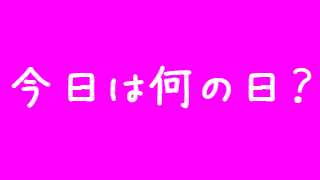 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 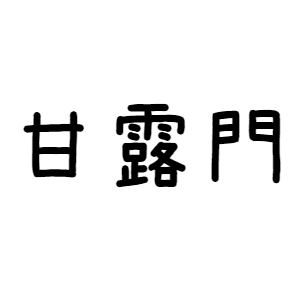 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『甘露門』(かんろもん)
甘露門は主に曹洞宗寺院で読まれるお経で、毎夕に行われる晩課、および施食会(施餓鬼会)、お盆の棚経でも読まれます。曹洞宗で読経される甘露門はお経や真言を一つの法要で読めるように編集したもので、古くは瑩山禅師の時代にもあったことが確認されています。ここで紹介する甘露門は写本等の差異を江戸期、明治期にかけて再編集されてきたもので、実際に僧侶も読んでいる大本山總持寺発行の経本を底本としたものです。①ルビ(読経の発音による かな読み)②本文(大太字)【 】はその部分の題名で、お経を連続して読む場合は読みません。また、人物や単語の解説が必要な場合はその言葉のリンク先を参照下さい。各宗派や時代によりお経の解...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『学道用心集』(がくどうようじんしゅう)
学道用心集は、道元禅師が興聖寺を開かれた翌年1234年に示されました。全10章の漢文による書物です。修行僧の心得を述べたもので、「菩提心を起こす可き事」にはじまり、「正法を見聞して必ず修習すべき事」「仏道は必ず行に依りて証入すべき事」「有所得心を用って仏法を修すべからざる事」「参禅学道は正師を求むべき事」「参禅に知るべき事」「仏法を修行して出離を欣求する人は須く参禅すべき事」「禅僧行履の事」「道に向かって修行すべき事」「直下承当の事」におわる。仏道修行に励む者の用心に不可欠な書です。<< 戻る
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 来迎(らいごう)- 来迎図
来迎とは、臨終の際に極楽浄土から阿弥陀如来が二十五菩薩と共に白雲に乗って、これから往生をとげようとする念仏の行者を迎えに来て極楽浄土に引き取ることです。その様子を描いたものを来迎図(らいごうず・らいこうず)といいます。「阿弥陀三尊」「往生要集」(絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図・知恩院)絹本著色 145.1×154.5cm 鎌倉時代(13-14世紀)この知恩院の来迎図は特に「早来迎」と呼ばれます。その表現には、鎌倉後期仏画の特色が表れ、往生をとげようとする者が経巻を前に端然と坐すさまや、右上の虚空中に宝楼閣(ほうろうかく)が出現していることにより、往生の階梯の最上位である上品上生図(じょうぼんじ...
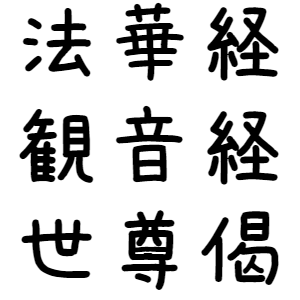 文献
文献 『観音経』(かんのんきょう/かんのんぎょう)
観音経とは、28にまとめられている妙法蓮華経(法華経)の1つである妙法蓮華経観世音菩薩普門品(25番目)の後半部分にある妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈の部分の事です。通称、観音経、または、世尊偈(せそんげ)といいます。ここには観音菩薩の名の由来と功徳が説かれています。 観音経には、底本が異なるなど、いくつかの版が存在します。宗派によってお経の読み方・読み癖が異なる場合があります。①ルビ(読経の発音による かな読み)②漢訳本文(大太字)③講話また、人物や単語の解説が必要な場合はその言葉のリンク先を参照下さい。各宗派や時代によりお経の解釈は違うものです、当ウェブサイトの一解釈としてご覧ください。なお...
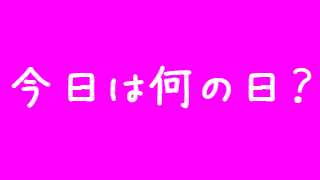 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 7月の出来事/有名人の誕生日・命日
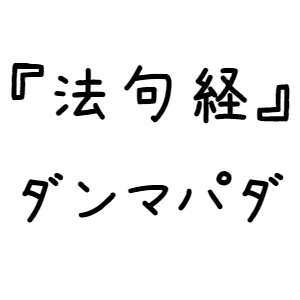 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『法句経』ダンマパダ – ブッダ 真理の言葉
かの尊師・真人・正しく覚った人に敬礼したてまつる。【 第1章 ひと組みずつ 】1 物事は心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人につき従う。車をひく牛の足跡に車輪がついて行くように。2 物事は心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも清らかな心で話したり行ったりするならば、福楽はその人につき従う。影がそのからだから離れないように。3 「彼は、我を罵った。彼は、我を害した。彼は、我に打ち勝った。彼は、我から強奪した。」という思いをいだく人には、怨みはついにやむことがない。4 「彼は、我を罵った。彼は、我を害した...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『正法眼蔵 』(しょうぼうげんぞう)
正法眼蔵は、道元禅師が23年間に渡りまとめ説かれたもので、1231(寛喜3)年8月に最初の巻である『弁道話』をあらわされました。最終巻は示寂の年1253(建長5)年1月に完成した『八大人覚』の巻です。その題名が示すように、釈尊から歴代の祖師をつうじてうけ継いだ正しい教法の眼目をあますところなく収蔵して提示しようとした書物ということが出来ます。その内容の多くは、道元禅師の深い悟りの境涯を、禅師独特の語法で説示した高度なもので、現代においても、日本の生んだ最高の宗教思想書とも評され、世界的にも高い評価がなされており、特に曹洞宗における根本的な聖典です。一般的には95巻とされていますが、それは道元禅...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『坐禅用心記』(ざぜんようじんき)/瑩山禅師
正和元(1312)年、瑩山禅師は能登(石川県)に永光寺(ようこうじ)を開き、そこで『坐禅用心記』を撰述しました。坐禅の心得を説いた指導書で、『普勧坐禅儀』と共に参禅する者にとって欠くことのできない教説です。坐禅の意義から、参禅の時の呼吸や姿勢、眼の開き方、手の置き方など、さらには食事や衣服などの注意にもふれられ、細かく丁寧に示されています。その全文を掲載いたします。①ルビ(かな読み)②書き下し本文(大太字)『坐禅用心記』それざぜんはじきにひとをして夫れ坐禅は直に人をしてしんちをかいめいし、心地を開明し、ほんぶんにあんじゅうせしむ。本分に安住せしむ。これをほんらいのめんもくを是を本来の面目をあら...
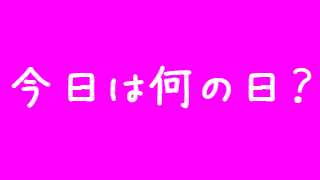 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 6月の出来事/有名人の誕生日・命日
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 雨が降る前に
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 雨で肌寒い日
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 艶やかな菩提樹
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ ブッダプールニマー(2026年は5月2日/土曜日)
ブッダプールニマーとは、上座部仏教圏(南伝仏教)でお釈迦様の降誕の日ならびに成道の日、涅槃の日として祝福される日です。ヴァイシャーカ月(4月中旬~5月中旬/「第2の月」)の満月に祝福されることから、ヴェーサーカとも呼ばれる他、ブッダ・ジャヤンティーとも呼ばれます。ブッダプールニマーは、インド、ネパール、シンガポール、ベトナム、タイ、カンボジア、スリランカ、ミャンマー、バングラデシュ、インドネシアなど、上座部仏教の仏教徒が多く暮らす国々を中心に、世界中で祝福されます。多くの場合、祝日で休みになります。私がクシナガラに滞在していた時には、ブッダプールニマーに因み、涅槃堂近くに特設テントが設けられ、...
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 雨の菩提樹
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 今日の菩提樹の葉
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 今日の菩提樹の葉
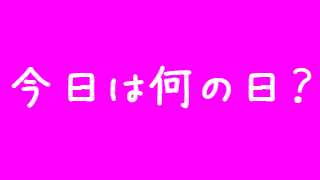 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 5月の出来事/有名人の誕生日・命日
 法要日記(供養/祈願/布薩)
法要日記(供養/祈願/布薩) 今日の菩提樹の葉です。新芽はまだ出ていないので、去年から越冬した葉です。
 法要サポート
法要サポート 誰でも布薩法要を実施できる動画(反省の日)(表白→三帰礼文→懺悔文[復唱]→開経偈→四弘誓願→般若心経→十善戒→回向→普回向→各自で反省、見つめ直す、見直す時間)
▶ 布薩法要(満月/新月に実施)▶ 布薩(ウポーサタ)
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 灌仏会(かんぶつえ/花まつり・花祭・釈尊降誕会)
4月8日は灌仏会です。釈尊、お釈迦様、ブッダ、色んな呼び名で呼ばれることがありますが、一番初め、生まれた時につけられた名前はシッダッタといいます。シッダッタが生まれたのは現在、ネパールという国のルンビニという場所です。全てはそこからはじまったわけです。仏教の開祖・釈尊の生まれた日には、寺院などでは法要をしたり、地域の人を集めて花祭りをしたりします。また、地方によってはひと月遅れの5月8日に花祭りが行われる場合があります。また、上座部仏教圏(南伝仏教)ではヴァイシャーカ月(4月中旬~5月中旬/「第2の月」)の満月にお釈迦様が生まれた日と伝えられていて、その日をブッダプールニマーといいます。<< ...
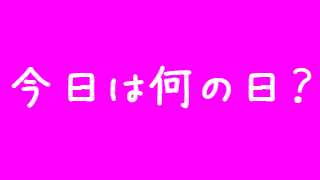 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 4月の出来事/有名人の誕生日・命日
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『阿弥陀経』(あみだきょう)
阿弥陀経は紀元後100年頃にインド文化圏で成立したと考えられている大乗仏教の経典です。もともとは梵語(サンスクリット語)で書かれていたお経で、 सूखावतीव्यूह, Sukhavati-vyuha, スカーヴァティー・ヴィユーハ(極楽の荘厳、幸あるところの美しい風景)というタイトルでした。鳩摩羅什による漢訳によって『阿弥陀経』となりました。同タイトルが付けられている『無量寿経』と区別して『小スカーヴァティー・ヴィユーハ』とも呼ばれます。略称は、『無量寿経』の『大経』に対して、阿弥陀経を『小経』とも呼んでいます。①ルビ(かな読み)②漢訳本文(大太字)③講話人物や単語の解説が必要な場合はその...
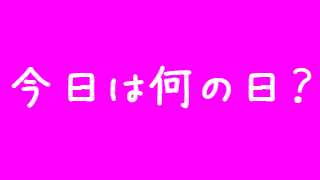 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 3月の出来事/有名人の誕生日・命日
 人物
人物 みのもんた
フリーアナウンサー、総合司会者、ニュースキャスター、タレント、実業家。主な出演番組『午後は○○おもいッきりテレビ』『どうぶつ奇想天外!』『学校へ行こう!』『クイズ$ミリオネア』『みのもんたの朝ズバッ!』『みのもんたのサタデーずばッと』『秘密のケンミンSHOW』など。2006年11月28日に「一週間で最も長時間、テレビの生番組に出演する司会者(記録:21時間42分)」という記録が、『ギネス・ワールド・レコーズ』に認定された。生誕 1944年〈昭和19年〉8月22日命日 2025年〈令和7年〉3月1日法号(戒名) 悠照院法道日国居士(ゆうしょういんほうどうにっこくこじ)<< 戻る
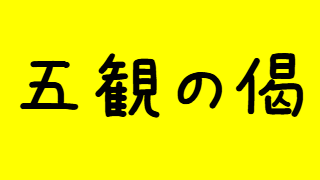 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 五観の偈(ごかんのげ)
ひとつには こうのたしょうをはかり、一には功の多少を計り、かのらいしょをはかる。彼の来処を量る。ふたつには おのれがとくぎょうの二には己が徳行のぜんけっとはかって くにおうず。全欠を忖って供に応ず。みつには しんをふせぎとがを三には心を防ぎ過をはなるることはとんとうをしゅうとす。離るることは貧等を宗とす。よつには まさにりょうやくをこととするは四には正に良薬を事とするはぎょうこをりょうぜんがためなり。形枯を療ぜんが為なり。いつつには じょうどうのためのゆえに五には成道の為の故にいまこのじきをうく今此の食を受く。これは五観の偈という食事に際して自分が反省すべき心得を箇条書にしたものです。禅宗寺院...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 菩提樹(ぼだいじゅ)
菩提樹はインドで古くからピッパラと呼ばれ聖木として扱われてきた樹の一つです。シッダッタがこの樹下で、坐禅を組んで全宇宙の真理(菩提)を悟り、ブッダとなったことから、後に悟りの樹、菩提樹(ボーディ・ブリクシャ)と呼ばれるようになりました。また、三大聖木の一つです。この写真はブッダガヤにある菩提樹です。この菩提樹のことを知る人に詳しく聞きましたが、この菩提樹は4代目だそうです。仏教にとって聖なる樹であっても、異教徒にとってはそうでない場合もあり、切り倒されてしまったこともあったようです。今ではその周りには坐禅をする人、お経を唱える人、観光に来た人、あらゆる人が常にいました。ここが仏教にとっての聖地...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 極楽浄土(ごくらくじょうど)
極楽浄土とは、阿弥陀如来が住む西方十万憶仏国土をすぎたところにあると言われる、苦しみのない安楽な世界です。梵語でスカーヴァティーといい「幸福のあるところ」「幸福にみちているところ」の意味があります。須呵摩提(しゅかまだい)、蘇珂嚩帝(そかばってい)、須摩提(しゅまだい)、須摩題などと音訳され、安楽、極楽、妙楽などと意訳されました。浄土とは、一切の煩悩やけがれを離れ、五濁や地獄・餓鬼・畜生の三悪趣が無く、仏や菩薩が住む清浄な国土のことで、大乗仏教の世界観を表現する言葉として使われていますが、平安後期以降に浄土教が広まると、浄土と言えは阿弥陀如来の西方極楽浄土をさすことが多くなったようです。また、...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ クシナガラについて
インド北部のヒマラヤ山脈とデカン高原に挟まれた場所にガンガーの流れる広大なヒンドゥスタン平原があり、そこにウッタル・プラデーシュ州(UP州)があります。この州はインド最大の人口を持ち、古くから農村地帯が広がり、稲作と畑作の混合地が多く、サトウキビや小麦などが作られてきた地域です。そんな農村地帯にクシナガラという町があります。(はじめの写真は2000年2月15日・涅槃の日に撮影)私がその場所に初めて行ったのが2000年2月でした。インドは年中暑いところだと思っていたので、意外と朝晩が寒くて驚いたのを憶えています。その後、この場所を何度も訪れることになるとは思ってもいないことでした。クシナガラへは...
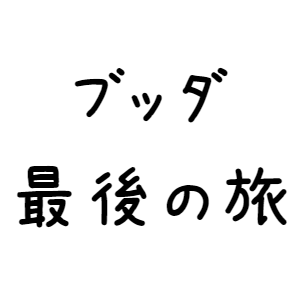 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ ブッダ最後の旅 – 大パリニッバーナ経
【 第1章 】1、鷲の峰にて1 私はこのように聞いた。ある時、尊師は王舎城の鷲の峰(霊鷲山)におられた。その時、マガダ国王アジャータシャトル(阿闍世)は、ヴァッジ族を征服しようと欲していた。彼はこのように告げた。「このヴァッジ族は、このように大いに繁栄し、このように大いに勢力があるけれども、私は彼らを征服しよう。ヴァッジ族を根絶しよう。ヴァッジ族を滅ぼそう。ヴァッジ族を無理にでも破滅に陥れよう」と。(2005年に管理人が撮影した鷲の峰/霊鷲山)2 そこでマガダ国王アジャータシャトルは、マガダ国の大臣であるヴァッサカーラというバラモンに告げて言った。「さあ、バラモンよ、尊師のいますところへ行け。...
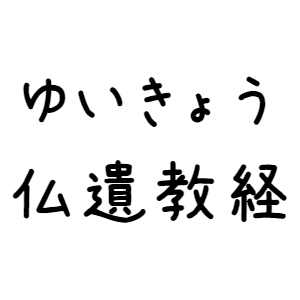 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『仏遺教経』(ぶつゆいきょうぎょう)
仏垂般涅槃略説教誡経(ぶっしはつねはんりゃくせつきょうかいきょう)を略したのが仏遺教経、さらに略して遺教(ゆいきょう)とも呼ばれる大乗仏教のお経です。お釈迦様が沙羅双樹の間に横たわり、弟子たちを前にして最後の教えを示した内容です。お釈迦様亡き後、弟子たちがどのようにすればよいのかを多くの譬えを使って分かりやすく具体的に説かれています。仏遺教経は涅槃会に読経される寺院が多くあり、特に曹洞宗ではお通夜に読経されることが多いようです。このように訓読を読まれる機会が多いことから、こちらではその訓読本文の全文と読経の発音によるかな読み全文を掲載します。①ルビ(読経の発音による かな読み)②訓読本文(大太...
 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 涅槃会(ねはんえ)
2月15日はブッダが涅槃に入られた日。涅槃会(ねはんえ)です。約2500年前、北インドを中心に教えを説いて歩き、多くの人々を救ったブッダはクシナガラの沙羅双樹の間で涅槃に入りました。今でもクシナガラは仏教の聖地に変わりありません。機会があれば行ってみてください。田舎町ですが、心が安らぐ場所です。まさしく涅槃の地であります。ちなみに日本では地方により、涅槃会の行事を旧暦に合わせて3月15日にする場合もあります。<< 戻る