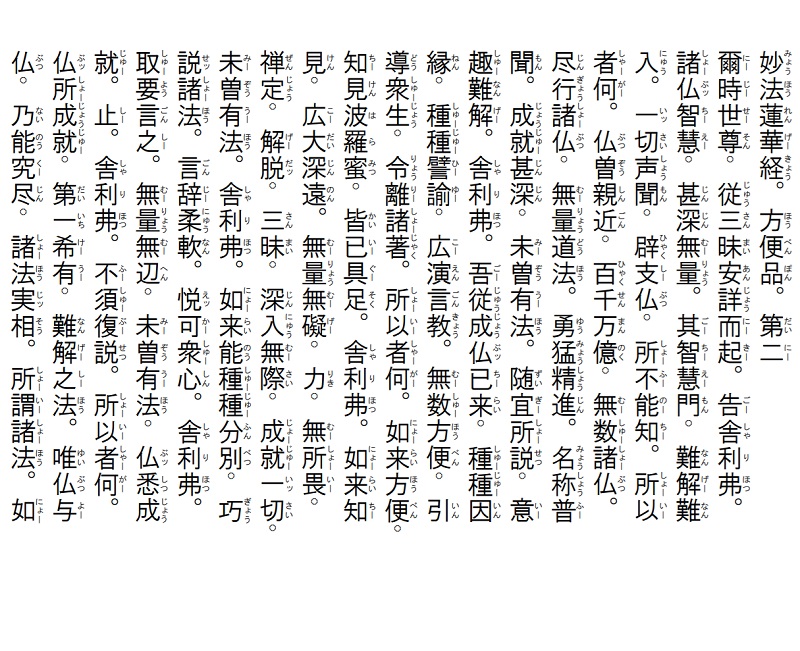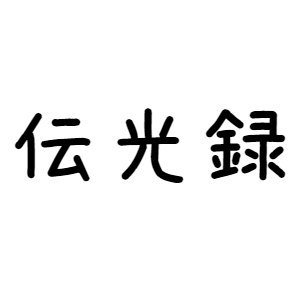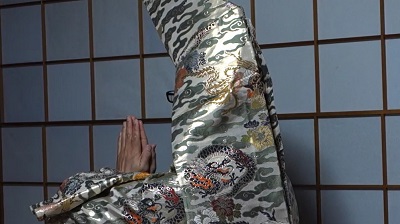 法要
法要 法要依頼/ご家庭や墓前へ出向いての法要
ご家庭や墓前へ出向いての法要をご依頼できます。メール打ち合わせの上、法要予定日時が確定した時点で約束は成立します。当然ながら、条件が合わなければお互いに打ち合わせ段階で断ることが出来ます。法要可能日/地域※ 現在、可能な日を掲載しています。掲載していない日も可能な場合があるため、まずは希望日時をお知らせください。土日祝日、平日、関係なく希望できます。※ 先約の予定が決まり次第、対応可能地域が限定されていきます。また、後から可能日を追加することもあります。2か月後以降であれば希望日時で予定を入れやすいです。※ 履歴や可能日傾向の参考として過ぎた月日も掲載したままにする場合もあるのでご了承ください...


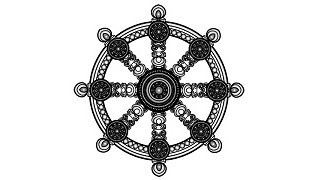
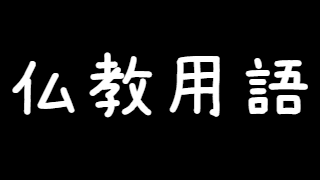


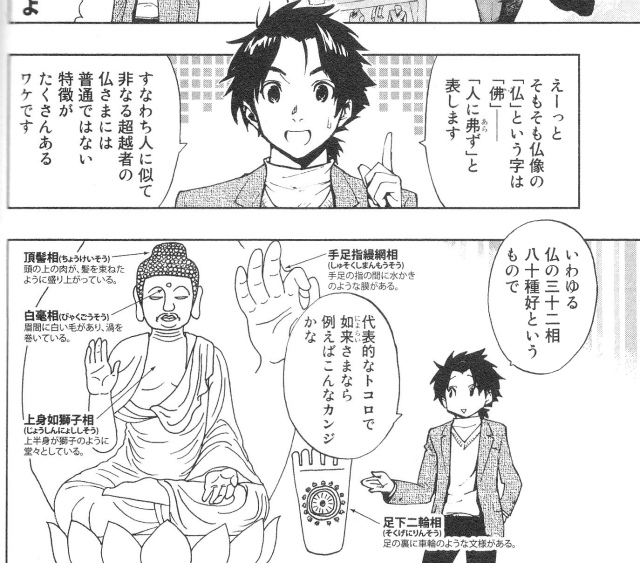


と梵天(右)wikipediaより.jpg)