 人物
人物 チャンナ
チャンナは、『ブッダ最後の旅【 第6章 】23、臨終のことば』に登場するお釈迦様の弟子です。チャンナは、気難しく、かたくなで、仏教教団の内部にあっても他人と協力せず、摩擦や抗争を起こしたことから、清浄な罰ブラフマ・ダンダを受け、その後は人格も円熟したと言われています。<< 戻る
 人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 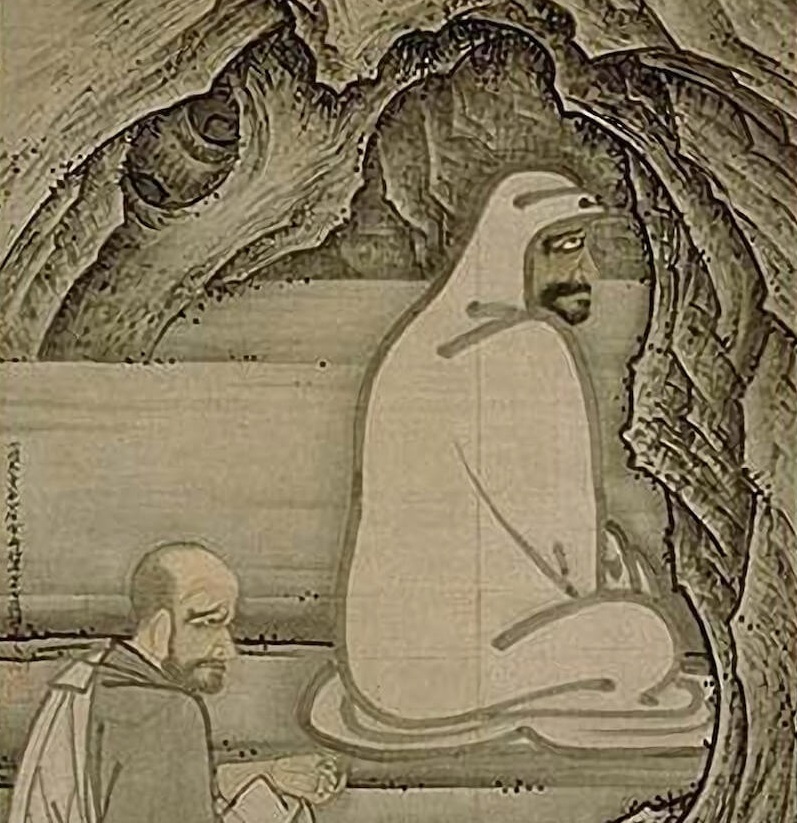 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 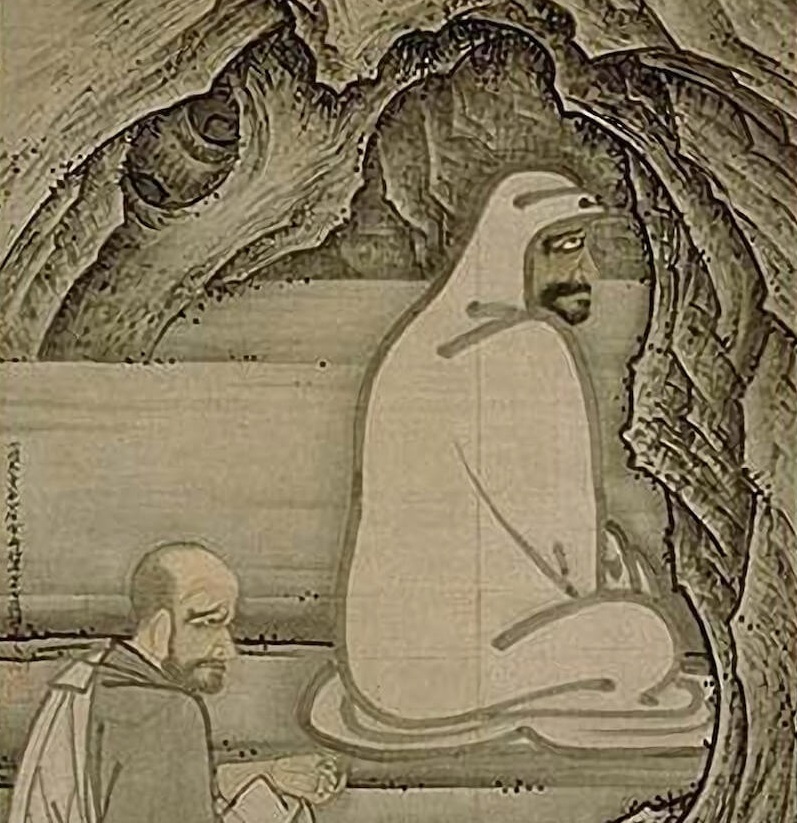 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ