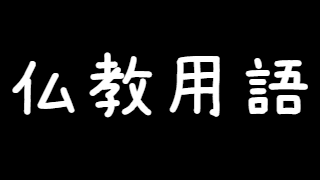 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 仏教用語/人物集 索引
このウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。
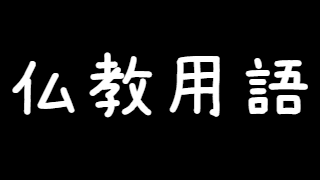 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 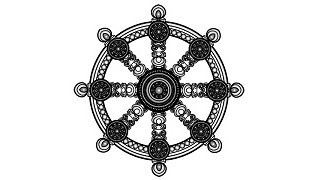 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 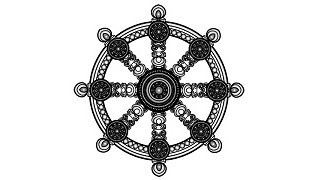 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 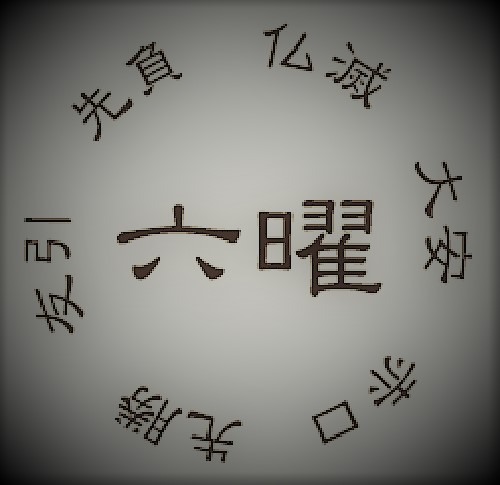 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ