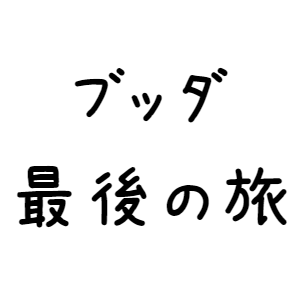仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 初転法輪(しょてんぼうりん)
初転法輪とは、仏(ブッダ)が成道後、はじめて教えを説いた時のことをいいます。その場所は、インドのバラナシ(ベナレス)の北方約10kmに位置するサールナートの鹿野苑で、その教えを聞いたのは五比丘だと伝えられています。また、仏が説法することを転法輪といいます。ブッダはブッダガヤでの成道後、最初に法を説く相手として、ウルヴェーラの苦行林(前正覚山)で共に6年間の修行を行なった五比丘のいる鹿野苑を訪れました。当初、五比丘は、修行を捨てたブッダが遠くから来るのを見て、軽蔑の念をも抱き歓迎を拒みましたが、ブッダの堂々とした姿を見て畏敬の念を抱いたことから、自然と座に迎えたといわれます。ブッダ自らが阿羅漢で...