寺院情報を宗派別に掲載。住所等を参考にしてご利用ください。
不動院 金峯山修験本宗 長崎県長崎市本河内町1258
西滝寺 中山身語正宗 長崎県長崎市千歳町7-4
善光院 中山身語正宗 長崎県長崎市中川町1-10-10
蓮聖院 光明念佛身語聖宗 長崎県長崎市上小島町4-16-9
明練寺 日蓮宗 長崎県長崎市江里町17-28
長光寺 日蓮宗 長崎県長崎市曙町32-2
妙晃院 日蓮宗 長崎県長崎市田上1-8-16
妙竜寺 日蓮宗 長崎県長崎市稲田町15-9
久本寺 日蓮宗 長崎県長崎市神浦江川町1310
自証寺 日蓮宗 長崎県長崎市琴海戸根町1096
瑞光寺 日蓮宗 長崎県長崎市川口町6-21
誠孝院 日蓮宗 長崎県長崎市東山手町7-23
得城寺 日蓮宗 長崎県長崎市神浦江川町1082
高泰寺 日蓮宗 長崎県長崎市高島町2117
岬忍寺 日蓮宗 長崎県長崎市脇岬町2288
円成寺 日蓮宗 長崎県長崎市茂木町224
長照寺 日蓮宗 長崎県長崎市寺町18
一妙院 日蓮宗 長崎県長崎市稲佐町303
法華経寺 日蓮宗 長崎県長崎市新戸町286-5
真乗院 日蓮宗 長崎県長崎市蚊焼町1797
本行寺 日蓮宗 長崎県長崎市西小島町2-1-4
昭徳寺 日蓮宗 長崎県長崎市飽ノ浦町8-23
妙光寺 日蓮宗 長崎県長崎市鳴滝町3-420
弘宣寺 日蓮正宗 長崎県長崎市鳴見町274-1
正霑寺 日蓮正宗 長崎県長崎市玉園町1-30
誠寿院 法華宗(本門流) 長崎県長崎市稲佐町306-3
妙薫寺 本門佛立宗 長崎県長崎市岩屋町779-10
古賀小僧伽 日本山妙法寺 長崎県長崎市船石町2071
長崎小僧伽(長崎道場) 日本山妙法寺 長崎県長崎市片渕町5-1108
高野平観世音 単立 長崎県長崎市本河内町1748
曉照院 単立 長崎県長崎市岩屋町44-20
地蔵寺 単立 長崎県長崎市入船町14-12
開目寺 単立(釋迦本教) 長崎県長崎市上小島3-3-25
一信寺 単立 長崎県長崎市芒塚町321
中里観音寺 単立 長崎県長崎市中里町463
観音教会 単立 長崎県長崎市矢ノ平2-7-22
霊法会長崎支部 単立 長崎県長崎市赤迫2-17-10
—–3—–
※各種法要、戒名授与、祈願や厄除け、魂入れ(開眼)、魂抜き(閉眼)、墓地、霊園、納骨堂、樹木葬、坐禅、拝観などで寺院所在地が知りたい場合等の確認にご利用ください。
新型コロナの影響で、寺院も例外ではなく、当ウェブサイトの過去の情報と現在の状況は異なっている場合があると考えています。※日蓮宗&諸宗派※
長崎県の特色 地域によって違いがあります
 長崎県のお盆といえば「精霊流し」が有名です。鐘と爆竹を鳴らしながら精霊船を引っ張り街中を練り歩く、長崎のお盆の伝統行事です。お墓参りでも爆竹を鳴らすので、「お盆は静かに」というイメージのある他の地域からすると驚かれることも。
長崎県のお盆といえば「精霊流し」が有名です。鐘と爆竹を鳴らしながら精霊船を引っ張り街中を練り歩く、長崎のお盆の伝統行事です。お墓参りでも爆竹を鳴らすので、「お盆は静かに」というイメージのある他の地域からすると驚かれることも。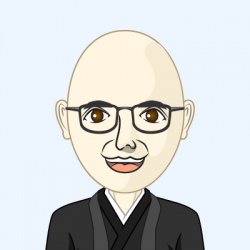 長崎県の一部には、故人の衣服を裏返しにして、7日間水を掛けて常に濡れた状態にしてつるしておく風習があるそうです。これを「水かけぎもん」あるいは「逆さぎもん」と呼びます。
長崎県の一部には、故人の衣服を裏返しにして、7日間水を掛けて常に濡れた状態にしてつるしておく風習があるそうです。これを「水かけぎもん」あるいは「逆さぎもん」と呼びます。 長崎県の一部では、出棺の際に近親者で棺を担ぎ、3度ぐるぐると回す「三度回し」「棺回し」などと呼ばれる風習があります。棺を回すことで故人の方向感覚を無くし、家に戻ってこられないようにするためで、迷いなくあの世へ旅立っていってほしいという願いがこめられていると考えられたり、回るという儀式を行うことで現世での罪をなくすための修行を行っているとする「減罪信仰」からとも考えられたりしています。
長崎県の一部では、出棺の際に近親者で棺を担ぎ、3度ぐるぐると回す「三度回し」「棺回し」などと呼ばれる風習があります。棺を回すことで故人の方向感覚を無くし、家に戻ってこられないようにするためで、迷いなくあの世へ旅立っていってほしいという願いがこめられていると考えられたり、回るという儀式を行うことで現世での罪をなくすための修行を行っているとする「減罪信仰」からとも考えられたりしています。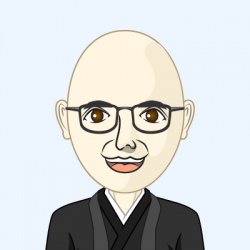 長崎県の一部地域では、出棺の際に遺族が額に△の白布つけるという風習が見られます。この△の白布は死装束のひとつで、仏教では「宝冠(ほうかん)」と呼ばれています。白布を身につけることによって、「故人が旅立つまでは、私たちも故人と共に見送りますが、そこから先はお一人で旅立ってください」という意味が込められています。
長崎県の一部地域では、出棺の際に遺族が額に△の白布つけるという風習が見られます。この△の白布は死装束のひとつで、仏教では「宝冠(ほうかん)」と呼ばれています。白布を身につけることによって、「故人が旅立つまでは、私たちも故人と共に見送りますが、そこから先はお一人で旅立ってください」という意味が込められています。