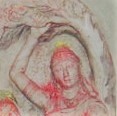仏教を学ぶ
仏教を学ぶ クシナガラについて
インド北部のヒマラヤ山脈とデカン高原に挟まれた場所にガンガーの流れる広大なヒンドゥスタン平原があり、そこにウッタル・プラデーシュ州(UP州)があります。この州はインド最大の人口を持ち、古くから農村地帯が広がり、稲作と畑作の混合地が多く、サトウキビや小麦などが作られてきた地域です。そんな農村地帯にクシナガラという町があります。(はじめの写真は2000年2月15日・涅槃の日に撮影)私がその場所に初めて行ったのが2000年2月でした。インドは年中暑いところだと思っていたので、意外と朝晩が寒くて驚いたのを憶えています。その後、この場所を何度も訪れることになるとは思ってもいないことでした。クシナガラへは...