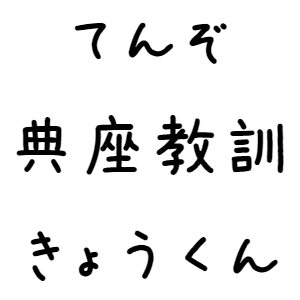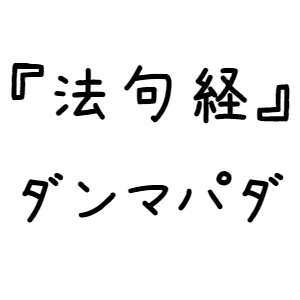人物
人物 松田優作(まつだゆうさく)
山口県下関市生まれの俳優、歌手。73年NTV「太陽にほえろ!」でジーパン刑事を演じてデビュー。同年、『狼の紋章』で映画デビュー。 74年『竜馬暗殺』、76年「暴力教室」、77年『人間の証明』などに出演、78年には『最も危険な遊戯』で村川透監督と初めてコンビを組み、以降『遊戯』シリーズや、大藪春彦原作角川映画『蘇える金狼』(79)『野獣死すべし』(80)と数々のハードボイルドアクションの傑作を発表し、ヒットを連発していく。生誕 1949年(昭和24年)9月21日命日 1989年(平成元年)11月6日天心院釋優道<< 戻る