 便り
便り 金相寺-神奈川県相模原市南区
・金相寺 浄土真宗東本願寺系単立 神奈川県相模原市南区麻溝台726-1【 寺号 】霊苔山 金相寺(りょうたいざん こんそうじ)【 宗派 】浄土真宗(東本願寺系単立)【 ご本尊 】阿弥陀如来(あみだにょらい)(リンク先より) << 戻る
 便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り 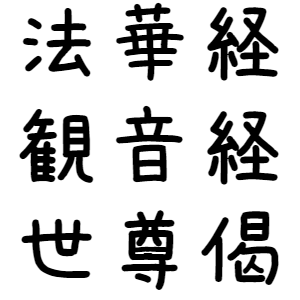 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り