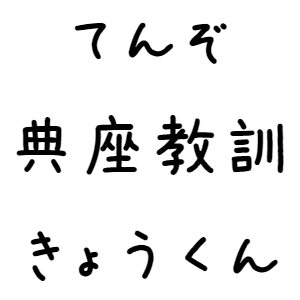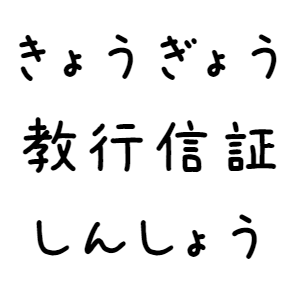人物
人物 日興(にっこう)
鎌倉時代の僧侶。日蓮の高弟六老僧の一人であり、白蓮阿闍梨と称する。日興門流の祖。富士大石寺の開山にして、日蓮正宗第二祖に列せられる。日興が日蓮のもとに赴いたのは、弘長元年(1261年)、日蓮が伊豆の伊東に流罪された時と伝えられる(日精『家中抄』)。日興は伊東において日蓮に給仕しただけでなく、周辺への弘教にも努力し、熱海の真言僧を折伏して日蓮の門下とした(日亨『富士日興上人詳伝』)。弘長3年(1263年)2月、日興は流罪を赦免された日蓮に従って鎌倉に入った。鎌倉での日蓮の活動拠点は松葉ヶ谷の草庵であり、日興もそこで日興より前に日蓮門下となっていた日昭・ 日朗らと共に日蓮に仕えながら日蓮の教化を受...