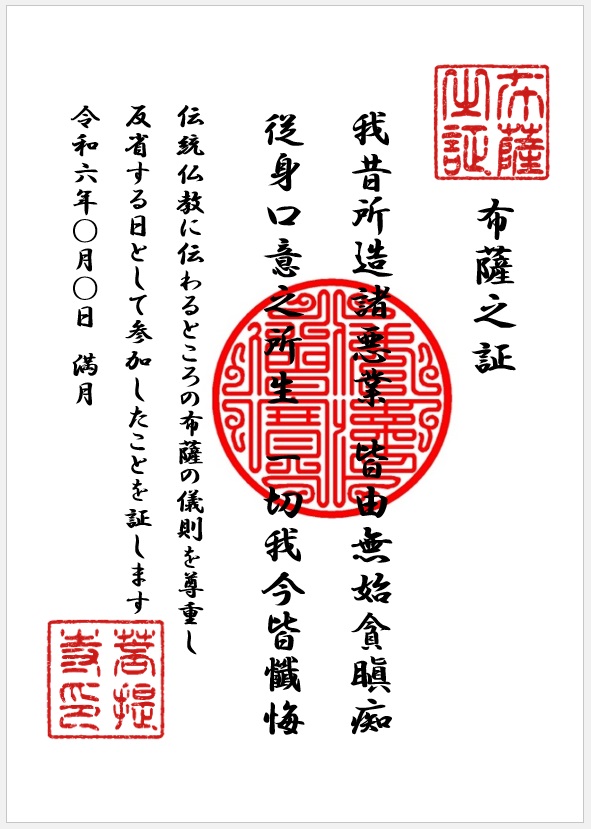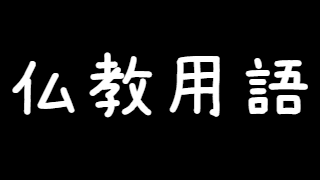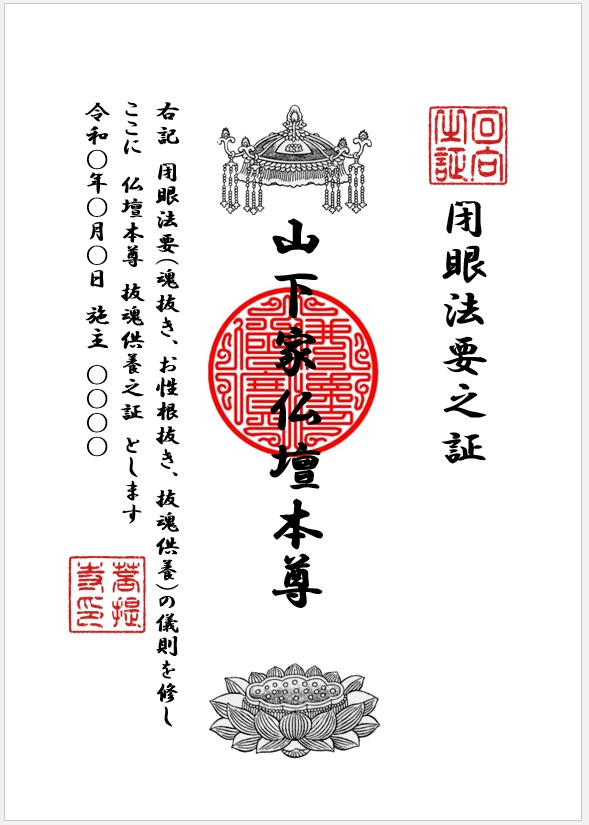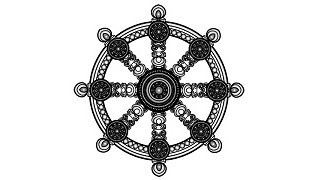仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ 灌仏会(かんぶつえ/花まつり・花祭・釈尊降誕会)
4月8日は灌仏会です。釈尊、お釈迦様、ブッダ、色んな呼び名で呼ばれることがありますが、一番初め、生まれた時につけられた名前はシッダッタといいます。シッダッタが生まれたのは現在、ネパールという国のルンビニという場所です。全てはそこからはじまったわけです。仏教の開祖・釈尊の生まれた日には、寺院などでは法要をしたり、地域の人を集めて花祭りをしたりします。また、地方によってはひと月遅れの5月8日に花祭りが行われる場合があります。また、上座部仏教圏(南伝仏教)ではヴァイシャーカ月(4月中旬~5月中旬/「第2の月」)の満月にお釈迦様が生まれた日と伝えられていて、その日をブッダプールニマーといいます。<< ...