 便り
便り 光泉寺-愛知県常滑市
・光泉寺 真宗大谷派 愛知県常滑市金山字平井111応仁元年1月(1467年)、現在の地に沸然上人(俗姓、藤原朝臣)を開山として創始される。時期については、「常滑市誌」に文明7年(1475年)より少し前(沸然上人の没年の少し前)に、と記載されている。(リンク先より)<< 戻る
 便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り 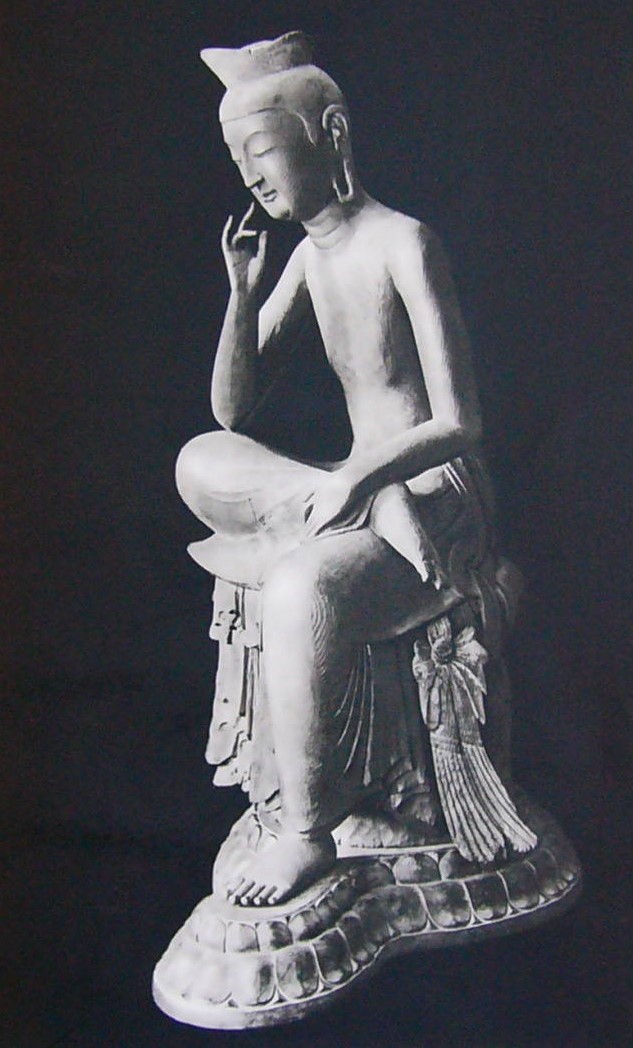 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り