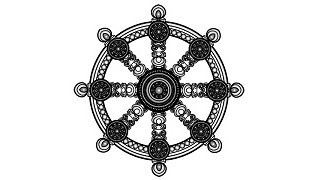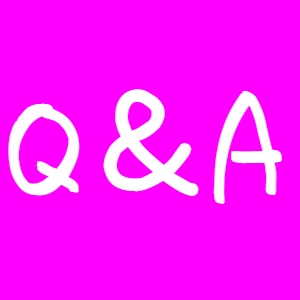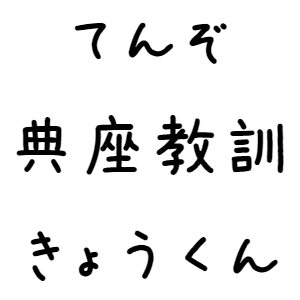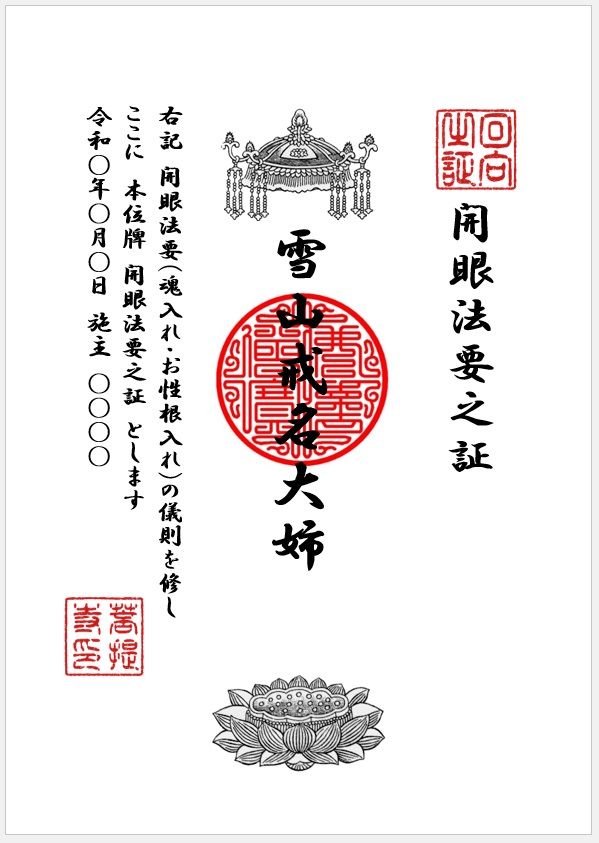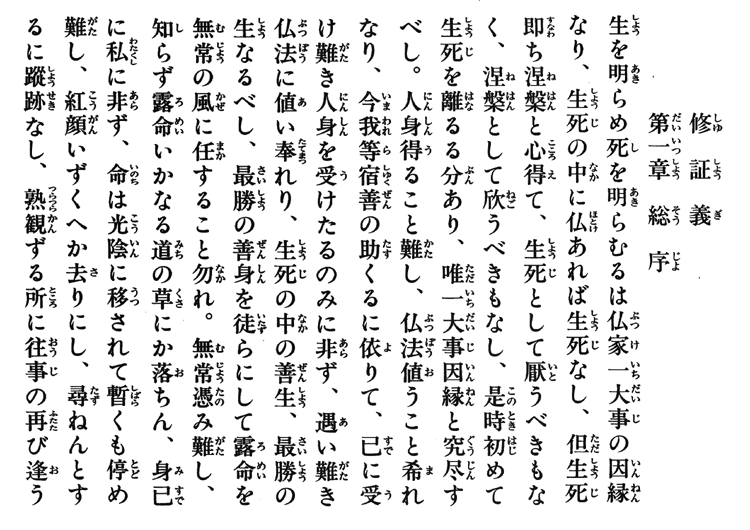 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 『修証義』(しゅしょうぎ)
『修証義』(しゅしょうぎ)は、おもに道元禅師の著わされた『正法眼蔵』から、その文言を抜き出して編集されたものです(どの部分から抜き出されたか詳しく知りたい方は ▶ 『修証義』(しゅしょうぎ)『正法眼蔵』対応版へ)。明冶時代の中ごろ、各宗派では時代に適応した布教のあり方を考える流れがありました。曹洞宗では曹洞扶宗会(そうとうふしゅうかい)が結成され、多くの僧侶や信者の人々がそれに参加しました。そのメンバーであった大内青巒(おおうちせいらん)を中心として『洞上在家修証義』(とうじょうざいけしゅしょうぎ)が刊行されました。これは在家教化のためのすぐれた内容となっていたため、曹洞宗では、ときの大本山永...