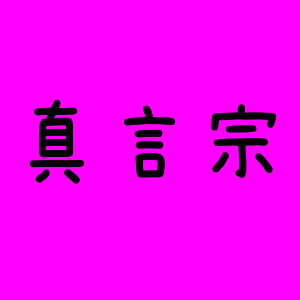仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 大日如来(だいにちにょらい)
大日如来について、このページでは主に造像さた仏像としての大日如来について書きます。もともとの梵名は「ヴァイローチャナ」または「マハーヴァイローチャナ」(諸説あり) といい、それを音写して「摩訶毘盧遮那如来(まかびるしゃなにょらい)」、「マハー」は「大きい」、「ヴァイローチャナ」は「太陽」の意味で、意訳して大日如来と呼ばれます。また、大光明遍照(だいこうみょうへんじょう)とも呼ばれることもあります。如来とは悟りを開いた仏の姿です。大日如来は、蓮華座に結跏趺坐し、頭に宝冠(ほうかん)、胸には瓔珞(ようらく)、 肩から手首までには臂釧(ひせん)、腕には腕釧(わんせん)をつけ、如来の中でも特別な王者の...