 人物
人物 石ノ森章太郎(いしのもりしょうたろう)
漫画家、特撮作品原作者。代表作は『サイボーグ009』『仮面ライダー』『人造人間キカイダー』『さるとびエッちゃん』『マンガ日本経済入門』『HOTEL』など多数。生誕 1938年(昭和13年)1月25日命日 1998年(平成10年)1月28日石森院漫徳章現居士<< 戻る
 人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物 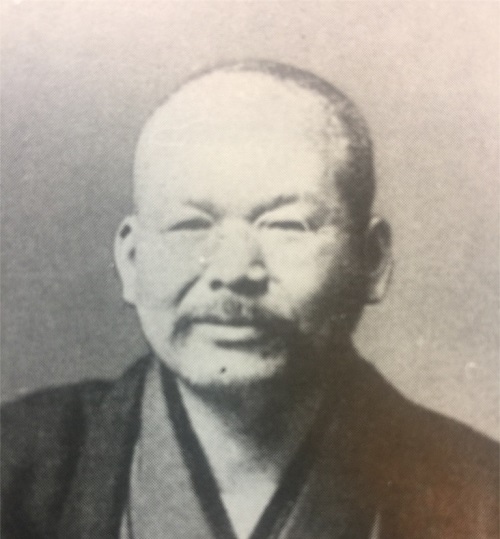 仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物  人物
人物