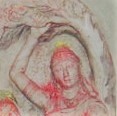仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ マガダ国(摩訶陀国)
マガダ国とは、古代インドにおける十六大国の一つ。紀元前682年~紀元前185年。ナンダ朝のもとでガンジス川流域の諸王国を平定し、マウリヤ朝のもとでインド初の統一帝国を築いた。仏典には「摩訶陀国」と表記される。ブッダ(お釈迦様)が活動していた頃の首都は、ラージャグリハ(王舎城)で、この都には竹林精舎があり、そして、近くには霊鷲山がある。仏典にはビンビサーラ王やアジャータシャトル王が登場する。その後、ウダーイン王は首都をガンジス川沿いのパータリプッタ(華氏城)へ移転させ、後に全インドの中心都市として栄えることになる。現在のビハール州の州都パトナに当たる。ブッダ(お釈迦様)とマガダ国紀元前536年、...