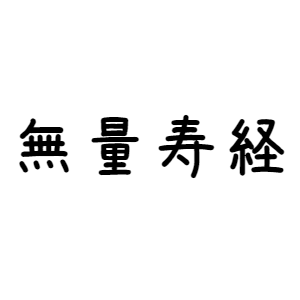仏教を学ぶ
仏教を学ぶ 方丈(ほうじょう)
方丈とは、もともと1丈4方の建物という意味で、禅宗寺院における住職/住持の居室、あるいは住職その人のことをこう呼びます。住職は方丈にて修行者を教えることから、単なる私室ではなく重要な伽藍の1つとなっています。正堂(しょうどう)、堂頭(どうちょう)、函丈(かんじょう)などともいいます。※1丈は約3メートル。方丈は、維摩経の主人公である維摩居士の住んでいた家がモデルとも伝わっています。昔インドで在家ながら仏教を深く信じていた維摩居士は、文殊菩薩をはじめとする8000人の菩薩や500人の声聞たちを、神通力をもって1丈4方の小室に招き入れたという故事によります。(『維摩経』「不思議品」)・「住持人は方...