 便り
便り 法蔵寺-栃木県日光市
・法蔵寺 浄土宗 栃木県日光市大桑町270法蔵寺は、正式には「真命山 心光院 法蔵寺」といいます。宗旨は浄土宗です。開創は、康応元年(1389年)10月です。日本国を二分した南北朝の戦いの折、南朝方に味方して敗れた「新田義貞公」の孫(義宗の子)良徳という方が、一族の菩提を弔うために仏門に帰依し僧侶となり、はるかに下向して下野国倉ヶ崎村(現在の日光市倉ヶ崎)に寺院「心光院」を建立したのが始まりと伝えられます。(リンク先より) << 戻る
 便り
便り  人物
人物  人物
人物  便り
便り  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り  便り
便り  便り
便り  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り  便り
便り 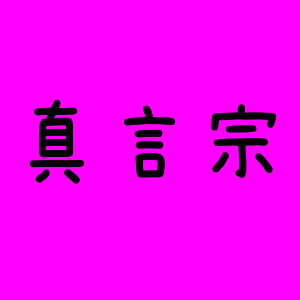 年表
年表  年表
年表  年表
年表  年表
年表  年表
年表  便り
便り  仏教を本気で学ぶ
仏教を本気で学ぶ  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り  年表
年表  便り
便り  便り
便り  便り
便り  便り
便り