 人物
人物 細川勝元(ほそかわかつもと)
室町時代中期の武将・守護大名。室町幕府16・18・21代管領。土佐国・讃岐国・丹波国・摂津国・伊予国守護。細川京兆家11代当主。応仁の乱の東軍総大将として知られている。生誕 永享2年(1430年)命日 文明5年5月11日(1473年6月6日)龍安寺殿宗寶仁榮大居士<< 戻る
 人物
人物  人物
人物 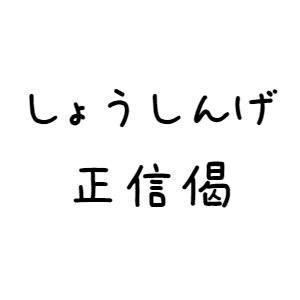 仏教を学ぶ
仏教を学ぶ