 つぶやき
つぶやき つぶやき
 つぶやき
つぶやき  つぶやき
つぶやき お坊さんの見習いにはまずお経の暗記が求められます。そこから成長していない住職が多くては困ります。お経の内容なんてどうでもいいと思う僧侶が多くては困ります。お経の内容を知っていて、説明出来て、あるいは行動で示して、はじめて僧侶として認められます。
 つぶやき
つぶやき お経はただ唱えればいいというものではありません。その作法は正しくても、そこに心が無ければいけないのです。素晴らしい内容を読んでいても、その意味を知らずに呪文のように読んでいてはいけません。大切なものを見失わないよう取り組むことはやりがいのあることです。
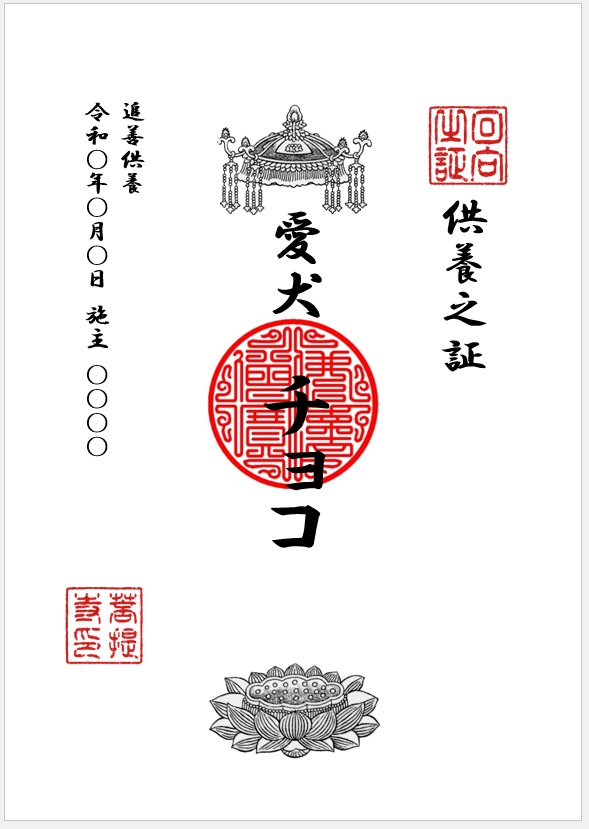 つぶやき
つぶやき ペットと言っても多種多様です。私の師匠の寺では野良犬を保護して育てていました。亡くなった時は境内の一画に埋葬して、毎朝、線香を供え、お経上げて供養していました。私のペット供養の原点です。
 つぶやき
つぶやき 一人ひとりが祈ることで心を整理する機会になって欲しいと動画を公開し、各種法要依頼を受け付けています。心を整えることで気兼ねなく生活を送ることが大事だと考えています。
 つぶやき
つぶやき あと、供養動画は形式的でもあります。伝統仏教が伝えて来た法要そのままという意味で形式的です。例えば、すべてを現代語にすることもできますし、歌にすることも出来るでしょう。しかし、形式を崩しては伝統仏教ではなくなってしまうところもあります。多くの人に認められてきた形です。形式的なものに気持ちを込めたら力強いものになりました。
 つぶやき
つぶやき 法要について、形式だけでは心が伴わないことがあります。「命日になるから供養しなければいけない」と感じるのであれば少し休憩しましょう。そんな義務感や形式ではなく、供養したいと思う気持ちが大事です。心が伴わない供養は意味がありません。供養動画は気持ちを込めて公開しています。
 つぶやき
つぶやき  つぶやき
つぶやき 以前、YouTubeでお経動画を公開していた時は、こんなお経もできる、この宗派も対応できる、というように選択と集中が上手くいかずに公開を打ち切っていました。今はシンプルに考えて、誰でも利用してもらえるお経動画を編集中です。
 つぶやき
つぶやき 伝統仏教にも問題があります。供養にしても、祈願にしても、布薩にしても、単なる儀式になってしまっている寺院が多くなっています。一人ひとりの気持ちの現れとしての、供養、祈願、布薩であってほしい、そういう場所を残さなければという思いで寺院センターの各種依頼を提供しています。合掌
 つぶやき
つぶやき 伝統的な位牌や仏壇はどうでしょうか?位牌は故人を仮に見立てたものです(そこには様々な意味が込められていますがここでは割愛)。仏壇はお寺の小さい版です。お釈迦様を代表的な本尊としますが、仏が教えを説く象徴であり、理想を形にした場所です。日本では先祖崇拝と合わさって、先祖が守ってくれているという象徴にもなっています。
 つぶやき
つぶやき オンラインの仏壇、墓石というものを何年も前に企画したことがありますが、今は類似サービスを含めておすすめしません。何故ならば、故人の写真や戒名(故人情報)を他人に預けて公開され、ウェブページやQRコードで読み取る等の方法でそれを確認するわけですが、自分で持っていればいいだけですよね。親戚に画像データなり、戒名を見せれば済む話なので、オンラインの仏壇やオンラインの墓石/霊園は必要のないものだと思います。
 つぶやき
つぶやき 普段お経を読む時はお経を唱えながら木魚を叩き、鐘を鳴らすので、木魚だけで聞くことはないことなので、動画のチェックのために木魚だけを聞いているとまな板で食材を切っている感覚になってきました。普段料理しているのでその影響か、それとも木魚のリズムと食材を刻むリズムが似ているのか!?
 つぶやき
つぶやき ちなみに動画のイメージ画像はロウソクを採用していますが、仏教の聖地クシナガラのド真ん中で灯されたロウソクです。停電中で灯していたロウソクが良い感じに動画で使えたというのはここだけの話です。
 つぶやき
つぶやき 休止していたYouTubeチャンネルを再開してみました。今のところ「祈る時間」と題した3つの動画を公開しています。「鐘の音」「木魚の音」「鐘と木魚の音」。何かの伏線になるのか!?▶ 寺院センター(YouTube)
 つぶやき
つぶやき 学問的な仏教は成果を発表することで学者は対価を得て生活している訳で、その途中を公開しても一銭の得にもならないのです。管理人は学者ではなく、ある意味で仏教の実践者だという自負からこのウェブサイトをまとめています。ただ公開するだけでは誰の意見も拾えず、ウェブサイト経費だけでも回収できる仕組みは続けていく上で必要かなと考えています。
 つぶやき
つぶやき 本日はブッダプールニマーです。特別に本日まで全ページを公開していましたが、古典を中心にパスワード保護のページを増やしたいと思います。誰でも条件をクリアすれば閲覧可能になりますので、その方法は現在公開のものとは変えます。追ってお知らせしますね。
 つぶやき
つぶやき パソコン作業は眼と身体への負担は大きいものです。適度に休憩をとるように心掛けていますが、ある作業がはかどった次の日、作業が全くできない程に眼と全身が疲れてしまうことがありました。やはり適度な作業が良いのでしょう。
 つぶやき
つぶやき 無量寿経の作業が一段落着いたら観無量寿経かな、その次は法華経の作業に・・・。他の作業も、仕事もあるので年内に形になれば。
 つぶやき
つぶやき お経にフリガナを振っていると「こう読むのか!?」と感心することがあります。日本にそのお経が入って来たタイミングでの読み方は現在の一般的な読み方と違って当然なのですが、違う時代に同じお経が入って来ても読み方が変わるので、現代読んでいる人にとってみれば「何で??」と思うことも多いかもしれませんね。多元的に読まなければいけません。
 つぶやき
つぶやき 普段使う漢字の読み方も、お経の中に出て来ると違う読み方をする場合が多いので、やはりフリガナは欲しいかなと思います。掲載している祖師の古典もそのうちに。
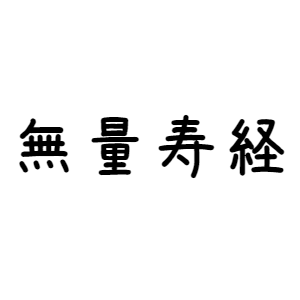 つぶやき
つぶやき 現在、『無量寿経』のふりがなを付けて誰もが読みやすくなるよう作業を進めています。長い目で見れば現代語まで付けたいと思っています。今月は祖母の命日もあった為、そういった気持ちも込めての作業です。なお、私の生家は浄土宗なので幼い時から聞いていたお経です。
 つぶやき
つぶやき リクエストにお応えして『正法眼蔵随聞記』にちくま学芸文庫版の章題番号を付加しました。より深く学ぶためにご利用ください。合掌
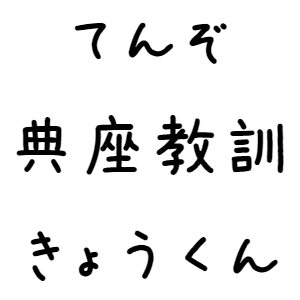 つぶやき
つぶやき 『典座教訓』のフリガナ振り終わりました。実際は太字の読み下し文の上に普通サイズの文字でひらがな『典座教訓』を掲載する形です。個人的には主に読み下し文を読みながら確認したい時だけフリガナを見て使っています。読むのに敷居が下がったと思うので是非!
 つぶやき
つぶやき 学校や仕事、家庭の中で学ぶことも同じで、全部「我がまま」「思いつくまま」でやる人は大抵上手くいきません。誰かに教えてもらったことをやってみて上手くいくと納得し、あるいは上手くいかないと反省して検証を重ねます。やらされているわけではありません。わたしたちはどんな場所にあっても表現者、アーティストです。
 つぶやき
つぶやき 学んだことの答え合わせは生活の中でする。多くの仏典を掲載していますが、単に文字の意味を知っていても役に立ちません。学んだことを生活の中に見つけて、自分で応用して、人に喜んでもらって、上手くいかなければ学び直して、そうやって更新して、先人は答えを見つけ、伝えて来たのです。
 つぶやき
つぶやき 典座教訓もそのうちフリガナ付けなければいけないかなと思っています。
 つぶやき
つぶやき みずから悪をなすならば、みずから汚れ、みずから悪をなさないならば、みずから浄まる。浄いのも浄くないのも、各自の事柄である。人は他人を浄めることが出来ない。(『法句経』ダンマパダ【 第12章 自己 】より)
 つぶやき
つぶやき 『阿弥陀経』を1か月で学べるように公開しました。漢文、ルビ、現代語を併記しています。1日1ページ読めば31日間で意味を確認しながら読み終わることが出来ます。合掌
 つぶやき
つぶやき 日本では自灯明・法灯明の教えとして伝わっている部分です。灯と島が指し示す所は同じで意訳されたのでしょう。ちゃんとブッダ最後の旅を読む前は、もっと最終的な遺言で語られた部分なのかなと思っていましたが、旅の途中でアーナンダに語った部分でした。もしかすると、それまでにも何度も説いていた教えかもしれませんね。
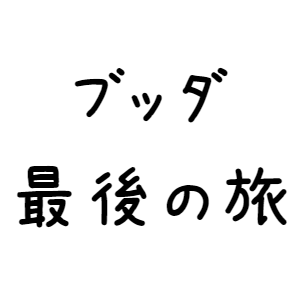 つぶやき
つぶやき 「今でも、また、わたしの死後にでも、誰でも自らを島とし、自らを頼りとし、他人を頼りとせず、法を島とし、法を拠り所とし、他のものを拠り所としないでいる人々がいるならば、彼らは我が修行僧として最高の境地にあるであろう。」(『ブッダ最後の旅』【 第2章 】9、旅に病む – ベールヴァ村にて)
 つぶやき
つぶやき