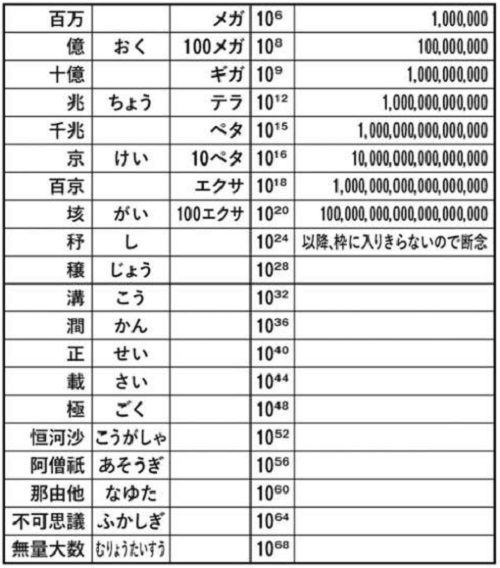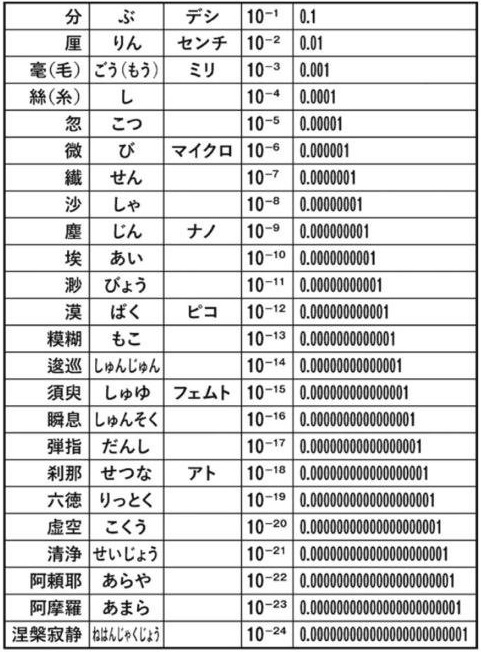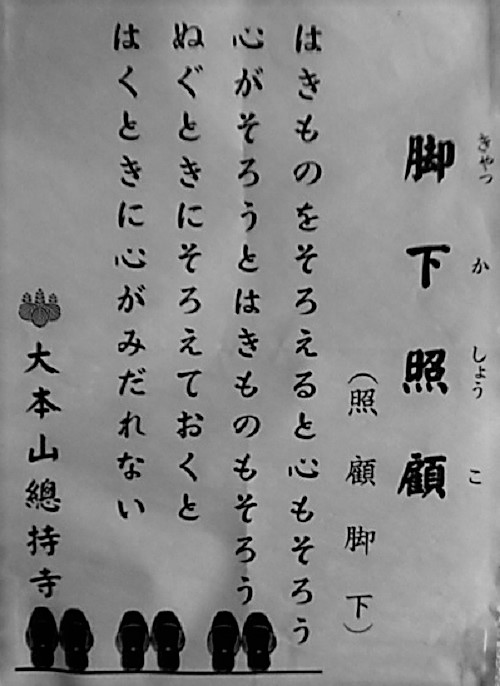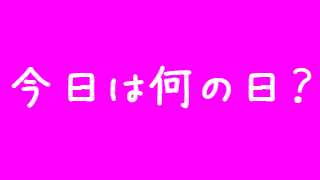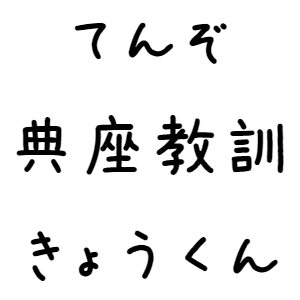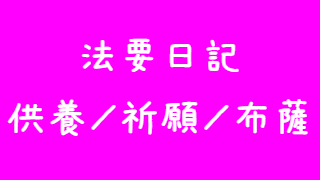 中島法雄
中島法雄 法要日記(供養/祈願/布薩)をはじめてみます
私にとって供養、祈願、布薩などの仏事は寺院生活を通して日常生活の一部になっているので、呼吸をするように自然なことなのですが、その法要をどのような気持ちでしているのか、どのような儀式的なことがあるか、どのようなタイミングで実施しているのか、そのようなことをアウトプットしていこうと思います。いずれは動画に切り替えることも考えていますが、編集のことを考えると時間を取られるのが厳しいです。まだ、このように文字や画像を使って伝える方が現時点では丁度良いかなと思っています。法要と言えば、着物を着てお袈裟を付けたたお坊さんがお経を唱えて、法要の主旨を読み上げて、儀式的なことをイメージされると思います。私が実...


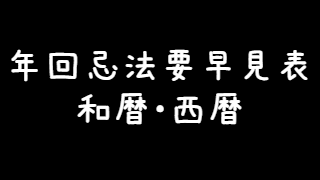




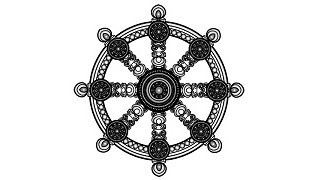




.jpg)